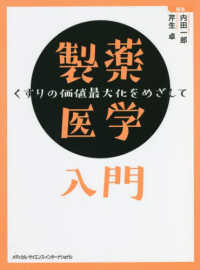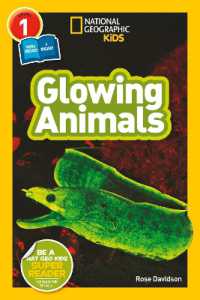出版社内容情報
フムスはひよこ豆にニンニク、レモン汁、塩、オリーブオイルを加えて作る中近東発祥の魅惑的なディップ。古代の近東からギリシャ、インドへと豆の栽培が広がるとともに伝わり、現代の健康的なグローバル食となるまでの歴史と文化。
内容説明
フムスはひよこ豆にニンニク、レモン汁、塩、オリーブオイルを加えて作る中近東発祥の魅惑的なディップ。古代の地中海沿岸からインド、ヨーロッパへと豆の栽培が広がるとともに伝わり、現代の健康的なグローバル食となるまでの歴史と文化。料理とワインについての良書を選定するアンドレ・シモン賞特別賞を受賞した人気シリーズ。
目次
第1章 ひよこ豆とタヒニの出会い
第2章 家庭のフムス
第3章 フムスの普及
第4章 戦争とフムス
第5章 フムス世代
著者等紹介
ヌスバウム,ハリエット[ヌスバウム,ハリエット] [Nussbaum,Harriet]
古代世界の食文化について幅広く執筆している。ブリストル在住
小金輝彦[コガネテルヒコ]
英語・仏語翻訳者。早稲田大学政治経済学部卒。ラトガース大学ビジネススクールにてMBA取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
秋良
19
世界ではメジャーな料理なのに日本ではマイナーな料理、フムス。スパイスで味付けしたひよこ豆のディップのこと。古代から豊富な栄養で人々の健康を支え世界中で大人気。それ故にレバノンとイスラエルでは「フムスはレバノン(イスラエル)料理だ」という諍いやプロパガンダへの利用もされてしまう。馬鹿馬鹿しいとも思うけど、食事を共にすることは文化を共有することに繋がるのでばっさりと切り捨てられない。クリーミーなペーストに塩とスパイスが程よく効いていて、ちょっとオリーブオイルが垂らしてある、CICADAのフムスが食べたい!2024/04/12
たかぴ
6
中東から地中海地方まで多くの国で食べられてきた料理を「私(だけ)の国の料理」ってレッテルを作ろうとするのは横暴だよな。レバノン、イスラエルどちらとも食べ物をプロパガンダに使おうとするのは興醒めだ。古くから共有してきた食事方法だからこそ価値が高いのに。2024/03/24
cybermiso
4
最近のフムスにこんなに種類あるとは知らなかった。海外スーパーにいってみたい レバノンとイスラエルはフムスでも争っている。レバノンはフムスを昔から作り食した国としてフムスの独占的所有権を主張したい。一方イスラエルは起源は主張しないがフムス輸出国として全世界にアピールしたい思惑がある。なおフムスはレバント地方から発祥したもので特定の国由来ではない。その中立性からフムスは最終的に中東の人を宗教(植物性由来なので戒律の影響を受けない)、階級、民族等関係なく結びつける可能性があるとのこと。そうなって欲しい。2025/12/02
ちり
2
“フムスは、何百年ものあいだレバント地方全域でつくられ食されてきたレバント料理であり、どこか特定の場所のものではなかった。比較的最近取り入れられた(19世紀初頭のヨーロッパによる植民地化の結果として)レバント地方にある国境は、必ずしも料理の線引きをするものではない。レバント地方の料理は密接に重なり合っていて、別の国の都市部の料理同士のほうが、同じ国の都市部と農村地域の料理よりも多くの共通点をもっていることもある。”2024/02/23
Οὖτις
1
イスラエルに行って以来フムスの虜。最近では乾燥ひよこ豆やタヒニも簡単に手に入るので、もっぱら自家製。ピタに山盛りで食べたいが、自家製の下手くそバゲットでもいける。作っている最中につまみ食いなんて量ではないくらい食べてしまう。市販品は好みではないし、簡単なので自分で作る。作者はフムス愛にあふれており、こちらもムフフとなる。2025/08/12