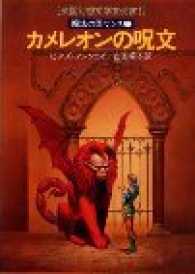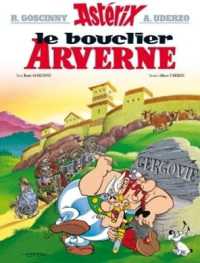出版社内容情報
紀元前四千年には存在していたというビスケット(クッキー)の歴史を紐解きながら、古代ローマからヨーロッパ、中東、そして現代のアメリカ、アジアまで、世界各地の歴史の旅へご招待。マカロンについてもふれる。レシピ付。
内容説明
甘くてサクサク郷愁の味。チョコチップクッキーは失敗作だった?ビスケットと南極探検の意外な関係?
目次
序章 主役でも主食でもなく
第1章 生存と祭礼―紀元前5世紀~1485年
第2章 甘さと軽さ―1485~1800年
第3章 黄金期―19世紀
第4章 国境を越えて―20世紀
第5章 神話と変容―21世紀
付録 死ぬまでに食べたいビスケット54
著者等紹介
エドワーズ,アナスタシア[エドワーズ,アナスタシア] [Edwards,Anastasia]
ライター、食物史家。ロンドン在住。ライター、ジャーナリスト、写真家、講師などで構成され、ワインやスピリッツを通じて交流する「サークル・オブ・ワイン・ライターズ(Circle of Wine Writers)」会員。BBCのラジオ番組に出演するなど、活躍は多岐にわたる
片桐恵理子[カタギリエリコ]
翻訳家。愛知県立大学日本文化学科卒。カナダで6年、オーストラリアで1年の海外生活を経て翻訳の道へ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
くさてる
24
紀元前4千年には存在していたというビスケット(クッキー)の歴史と種類を紹介した一冊。要するに小麦粉と水を練って焼いたもの。だけど、それがさまざまな工夫と風土、宗教、文化の違いなどから、種類を広げ、愛されてきたかが良く分かります。付録の「死ぬまでに食べたいビスケット54」が楽しかった。6種類しか食べたことがなかったので、増やしたいです。2020/09/19
パトラッシュ
15
酒なんぞ苦い水でしかない下戸の自分にとって、甘いものの話は楽しく面白い。この<お菓子の図書館>シリーズでもケーキとチョコレートの話を読んでいたが、やはり普段よく食べるのはビスケットとクッキーなので興味津々でページを繰った。何の気なしにつまんでいるビスケット類にも、こんな開発の歴史があったのかと思わず笑ってしまう。海外旅行へ行く際も現地のお菓子をいろいろ食べてきたが、これからはどこにどんな菓子があるのか調べてからにしようか。史跡や自然の観光と同じく、その土地で生まれ名物となった菓子をじっくり味わうためにも。2020/02/09
みなみ
13
お菓子の図書館シリーズは昔けっこう読んでた。図書館で見つけたのでこちらも。読んでいて、マカロンがビスケットに分類されるのが驚いた。歴史上古くからあるシンプルなお菓子としてのビスケットから始まり20世紀の大量生産時代まで進み、ビスケットの缶パッケージにも言及される。お菓子の成り立ちや歴史なので読みやすいのと、パッケージやブランドロゴも含めて写真が多いのがこのシリーズの持ち味。巻末を読むと、世の中にはこんなにビスケットがあるのかと思わされる。2023/08/31
リリウム
9
お菓子界において大御所のような存在だと思っていたクッキーやビスケットが本格的に開花したのは比較的最近であるということに、少なからず驚きましたが、その大御所感はかつて、なくてはならない保存食品として確かに鎮座してきた歴史による安定感ゆえなのだろうと納得もできました。2020/07/08
いーたん
8
イギリスの食文化ライターによる著書。ビスケットもクッキーも同じもので、アメリカではクッキーと称するが、著者はイギリス人らしくビスケットで文言統一されている。もともと、船乗りの保存食だったものが、砂糖の普及によって庶民にも親しまれるようになり、さらにお菓子メーカーによって、世界の子どもたちのおやつとして定着していく様を、豊富な写真とともに紹介。どれも美味しそう❤️アメリカのナビスコがナショナルビスケットカンパニーの略だと知って納得。ずっと、ナビスコの名前の由来が気になってたので。2020/05/23