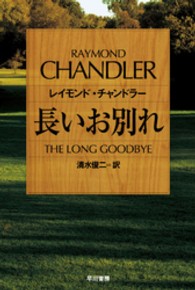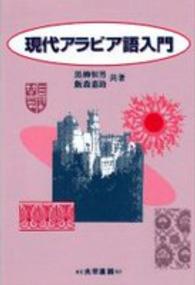出版社内容情報
「人類は戦争に魅了されている」だから文化が生まれるのだと著者は言う。戦争に伴う儀式は、まさに戦争が文化そのものだと。戦争は政治目的の手段に過ぎないというクラウゼヴィッツに異議を唱え、「戦争とはなにか」を喝破した名著。
内容説明
軍事史・戦略論の世界的権威が語り尽す。誰もが戦争に魅了される。なぜ芸術家はこぞって戦争を描き出そうとするのか。そこに真の人間の姿を見るからではないか。
目次
第4部 戦争のない世界?(平和だった時期はほとんどない;大規模戦争の消滅;常識が通用しない;ヒトはどこへ向かうのか?)
第5部 戦争文化をもたぬ世界(野蛮な集団;魂のない機械;気概を失くした男たち;フェミニズム)
結び 大きなパラドックス
著者等紹介
クレフェルト,マーチン・ファン[クレフェルト,マーチンファン][Creveld,Martin van]
イスラエルのヘブライ大学歴史学部教授。専門は軍事史および戦略研究。ロンドン大学経済政治学学院(LSE)で博士号を取得した後、1971年から現職。また、アメリカなど主要諸国政府の防衛問題アドバイザーとしても活躍
石津朋之[イシズトモユキ]
獨協大学卒、ロンドン大学SOAS及び同大学キングスカレッジ大学院修士課程修了、オックスフォード大学大学院研究科修了。防衛省防衛研究所戦史部第一戦史研究室長。拓殖大学、上智大学、放送大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メロン
8
上では概論的な話が多く下になると本論に入り非常に興味深い内容であった。著者のクレフェルトはクラウセヴィッツのような戦争を政治の延長で考える現代の戦争観を厳しく批判する。戦争が政治の手段として合理的なものであるとすればなぜ戦士はきらびやかな戎衣をまとう必要性があるのだろうか。その上で戦争をとらえるにはより大きく文化論としてとらえるべきであることを主張する。そして、その戦争文化のもたらす変容を4つの類型から述べる 軍国主義と断罪するリベラルも、戦争を単純化するリアリストにもこの問いに対しては向き合うべきだろう2023/10/14
無重力蜜柑
8
「戦争それ自体の文化」を論じるクレフェルトの著作の下巻。上巻では無数の事例を列挙して「戦争文化とはどのような要素から成るか」を解説していたが、下巻では「もはや戦争は起きない」という説への反論と、「戦争文化が失われた社会はどうなるか」というテーマについての考察。前者についてはいわゆる「非対称戦争」的な議論で、現代からすればそこまで目新しいわけでもないと感じる。後者についてはかなり偏った主張だなあと思うものの、「中東戦争時代のイスラエル」にルーツを持つ著者の来歴を思えばそれなりの妥当性もあるのかもなと。2021/07/28
yo
4
戦争のない世界が来うるのか、そして、戦争文化を失った社会はどうなってしまうのかを検討する。戦争のない世界は来得ない、なぜなら、人々は戦争に魅力を感じるから。WWII以降国家間戦争が減っているのは、核兵器の登場によって人類が滅亡することを恐れるからであって、戦争の魅力が衰えたわけでも、人類が平和を真摯に希求するようになったからでもない。そして、戦争文化を失うと、「野蛮な集団」になったり、「魂のない機械」のように腑抜けた兵士になったり、「気概のない男たち」になったり、「フェミニズム」が台頭したりしてしまう。2016/04/17
富士さん
1
ワタシは万人の万人に対する闘争という意味で戦争を捉えており、ゲームや商売、儀式や趣味を含めて広範に戦争文化を語る著者とも共通する部分があると第四部の終わりまでは思っていました。が、どうも著者は集団と集団でないと戦争とは定義されないようで、個人単位の戦争文化を語られていたにもかかわらず第五部に至っては野戦にしか触れられず論じられており、自分とは戦争の捉え方が違って全く共感できませんでした。個人が行う尊厳ある生存への戦いこそ戦争の原子であり、だからこそ戦争は楽しいんであって悲惨なんだと思うんですけれども。2013/12/13
メロン泥棒
1
人類が大好きな戦争の話。下巻。核兵器の登場によって、大国間の戦争は無くなり、戦争を否定する風潮が増えた。戦争の魅力が無くなり、戦争文化が消えようとしているのかという問いには断固として否を唱える。戦争文化の放棄の結果は次の4つがある。第1に野蛮な集団、第2に魂のない機会、第3に気概を無くした男達、第4にフェミニズム。特に戦争文化を放棄したドイツと世界の現状を元に、戦争文化の重要性を改めて説く。2010/09/11