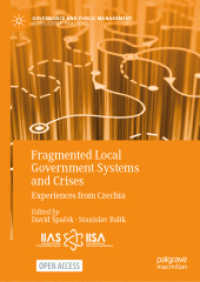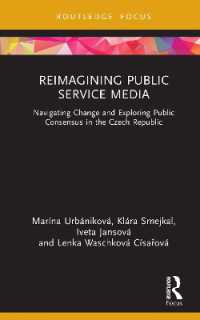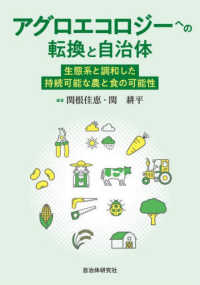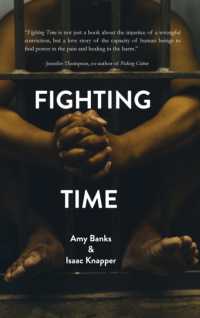内容説明
シビル・ミリタリー・リレーションズの展開を、欧米の近代史のなかに初めてあとづけ、健全な文民統制のあり方を明らかにした画期的な書。
目次
第2部 アメリカにおける軍事力―歴史的経験(一七八九‐一九四〇年)(新ハミルトン主義的妥協の失敗(一八九〇~一九二〇年)
第一次大戦と第二次大戦との間におけるシビル・ミリタリー・リレーションズの不変性)
第3部 アメリカのシビル・ミリタリー・リレーションズの危機(一九四〇~一九五五年)(第二次大戦―権力の錬金術;第二次大戦後の十年間におけるシビル・ミリタリー・リレーションズ;統合参謀本部の政治的役割;権力の分立と冷戦下の国防;国防省におけるシビル・ミリタリー・リレーションズの構造;新しい均衡へ向って)
著者等紹介
ハンチントン,サミュエル[ハンチントン,サミュエル][Huntington,Samuel P.]
1927年生まれ。アメリカを代表する国際政治学者。2006年までハーバード大学政治学教授。1977~78年には、カーター政権下の国家安全保障会議のコーディネーターを務めた
市川良一[イチカワリョウイチ]
1956年京都大学農学部農林経済学科卒。航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程を経て、1970年幹部学校教官となり、指揮・管理、オペレーションズ・リサーチを担当。気象中枢等を経て、1975年から幹部学校教官として軍事史を担当。元防衛庁防衛研修所員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
蟹
2
アメリカという、自由主義を至高の価値とする国家にあっては、根本的に相容れない存在である(はずな)のが軍人という職業集団である。そこでいかにあるべきかを考察する本書の下巻においては、米国に終始着目し、ついには基本的に文民である国防長官がその(本書上梓時においては)短い歴史でいかに苦悶してきたかを説く。米国の政軍関係は決して最初から安定したものでなかったことを本書は如実に語っている。さまざまな視点を紹介する本書において、しかし一貫して軍人に求められているのは、そのプロフェッショナリズムを磨くことである。2018/06/11
Bokushow
1
上巻に引き続き、難しかったです2015/03/13
Merkava
0
戦前の日本陸軍、とりわけ参謀本部はプロフェッショナリズムを追求した組織ではなかったのか、あれは客体的文民統制ではないのかと、多少の疑問を感じざるを得ませんが、それでも新しい視点を得られたので有用な本でした。2011/06/19
てっき
0
(上巻とあわせて)課題のため読んだ本。シビル・ミリタリー・リレーションに関する大著。上の前半までは全般的な話と日独の政軍関係について、以降はひたすら米国の軍事を焦点とした政軍関係に関する変遷について客観的シビリアンコントロールの視点からの分析であった。本著の特性として言われる軍人の3つの機能などは正直主題ではなく、米国における政軍関係の今後に対する提言、というのが主題であったと感じた。ゆえに、日独の政軍関係についてはバッドケースとして描かれており、(現在の研究からは)事実誤認と思われる描写もあった。2020/09/05