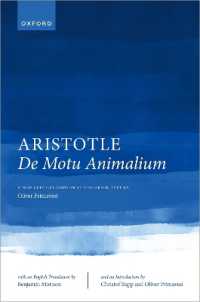出版社内容情報
西欧史・中国王朝史中心の従来の世界史像を見直し、イスラーム史を適切に組み込むことで、バランスの取れた新しい「世界史」を展開する。
内容説明
文明と世界史の新たな視座へ。大航海時代に先駆けてユーラシア大乾燥地帯をラクダとウマと帆船の回廊で結んだイスラームの大商圏…。
目次
第1章 新しい世界史を求めて
第2章 アラビア半島からの世界史の転換
第3章 ユーラシア商圏の登場
第4章 ユーラシア規模に広がる世界
第5章 情報の大交流が生み出したイスラーム文明
第6章 イスラーム大商圏を再編したモンゴル帝国
著者等紹介
宮崎正勝[ミヤザキマサカツ]
1942年東京生まれ。東京教育大学文学部卒業。筑波大学附属高等学校教諭(世界史担当)、筑波大学講師などを経て北海道教育大学教授。2007年に退官、現在は著述業、中央教育審議会専門部会委員。1975年から88年までNHK高校講座「世界史」常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
15
イスラーム世界の成り立ちをしっかり理解したく図書館本。分かりやすい本でした。メソポタミアに始まる人間の文明は、国の拡大、宗教拡散とどの目的をかえ、戦争、紛争の歴史が脈々と受け継がれている。現代をも占う中東情勢、いやっ、イスラーム情勢は目を見張る。2017/02/16
futabakouji2
9
イスラームの勃興からモンゴル時代の終焉まで描く。東ローマとササン朝が激突し、疲弊した時にイスラームが拡大する。西はイベリア半島、東はアフガニスタンを勢力下に治めて、砂漠の遊牧民とガウ船で陸と海のその領域をイスラームネットワークが覆う。 日本の教育ではイスラームはあんまり触れないが、この地域の歴史がわからんと世界史のことがさっぱりわからないので、読むのにオススメ。2018/07/09
yasu7777
4
★★★☆☆ イスラームを世界史舞台引き上げる力作。宮崎氏の著作は読みやすい。2016/08/21
閑
3
「世界の一体化」の前史としてのモンゴル帝国のさらに前に、アッバース帝国とイスラム商人によるユーラシア規模のネットワークが存在したことを指摘する本。東は中国、南は東アフリカ、西はイベリア、北はバルト海までを含む大商圏が具体的な例を挙げながら叙述されている。魔法のランプのアラジンが住んでいたのは中国だったり、スウェーデンから大量のアラブ銀貨が出土していたりとイスラム商人の商圏の広さに驚かされる。東洋史・西洋史の端々で顔を出すイスラムが実は「世界史」の前史を形作る大立役者だったことを教えてくれる好著だった。2011/10/18
rytryt
2
イスラム世界の発展とユーラシア世界の関係をわかりやすく記述してあります。読みやすく世界史入門の一つとしておすすめ。 イスラム社会の成り立ちは商業(砂漠の交易)社会にあり、イスラム社会の発展は、商業ネットワークの発展とともにある。ユーラシアではイスラム王朝からモンゴル(元)の大商圏の発展があり、その中でイタリア諸都市が力を蓄える。その後、オスマン帝国の登場することにより、イタリア諸都市は新しい市場を求めることになり、大航海時代に繋がっていく。2024/02/27



![ぜんぶ話して![ライト版]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45600/4560061564.jpg)