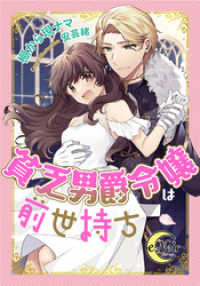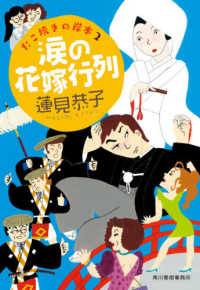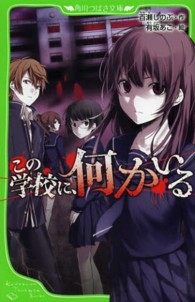出版社内容情報
イタリアでは70年代に入ってから、経済性偏重の都市政策の結果、都市の過密と農村の過疎が顕著となった。それをきっかけに、歴史、文化、環境、住民意識等の非経済的な価値を重視する地域政策への転換へと舵を切ることになる。その鍵となったのが、テリトーリオ概念である。これは、地域の文化、歴史、環境、その土地の農産物の価値を高め、都市と農村の新しい結びつきを生む社会システム概念である。そしてそこには、地域住民が主体的に活動するロジックが含まれている。
本書では、イタリアにおける、テリトーリオを起点とした、経済的価値と非経済的価値とのバランスのとれた社会へのパラダイムシフトのプロセスを、都市・建築・地域政策、経営学、観光、料理・ワイン等を専門とする日本とイタリアの研究者・実務家たちが、多面的に描き出す。彼らは既成の体系に囚われることなくそれぞれの切り口で、しかし歴史という視点には重きを置きながら議論を展開していく。
イタリアと日本は、「石の文化」と「木の文化」の違いという点で、対極にあるとよく言われる。しかし近代化のあり方、豊かな自然と長い伝統を有することなど、共通点も多く指摘されている。経済効率性重視の地域活性化策の行き詰まりに悩む日本への示唆に富んだ、学際的研究による新しい文明論。
内容説明
イタリアはいかにして地域のポテンシャルを再評価し都市文明からの脱却を果たしたのか?ワインと郷土料理のエノガストロノミアが都市と農村を結び付けコモンズの精神を再生させる。日本への示唆に富む学際的研究による新文明論。
目次
農産物の生産と流通をテリトーリオの文脈で再考する
第1部 テリトーリオの理論的枠組みと分析概念(チェントロ・ストリコからテリトーリオへ―田園の再評価とその再生;テリトーリオの内発的発展―農業の多機能性による地域の持続可能性;テロワール産品を通じたルーラル・ジェントリフィケーション―イタリアのキアンティ)
第2部 テリトーリオ理論の実践的な展開(農村ツーリズムとテリトーリオ産品の価値向上のためのネットワーク;質の良い地域産品、新しいライフスタイル、エノガストロノミア・ツーリズム―アドリア海沿岸のいくつかの州におけるオルタナティブな発展;アフターコロナ時代のテリトーリオとフード・ツーリズム―ローマ大都市圏近郊の事例)
第3部 テリトーリオの象徴としての食文化とワイン(イタリア食文化の価値―郷土料理を読む方法論;イタリアワインの多様性とテリトーリオ)
鼎談 テリトーリオ・ルネサンスが紡ぐ未来
現代都市文明からの脱却、農業の再評価―イタリアから日本へ
著者等紹介
木村純子[キムラジュンコ]
法政大学経営学部教授。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。博士(商学)。パドヴァ大学大学院客員講師、フランス農業専門職大学院(´Ecole Sup´erieure d’Agriculture)客員講師、2012年から2014年までヴェネツィア大学客員教授。専門はテリトーリオ、地理的表示(GI)保護制度、地域活性化、SDGs。農林水産省の地理的表示登録における学識経験者、財務省の国税審議会委員他
陣内秀信[ジンナイヒデノブ]
法政大学江戸東京研究センター特任教授。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。イタリア政府給費留学生としてヴェネツィア建築大学に留学、ユネスコのローマ・センターで研修。専門はイタリア建築史・都市史。パレルモ大学、トレント大学等の契約教授を務めた。国交省都市景観大賞審査委員長他。受賞歴:地中海学会賞、イタリア共和国功労勲章、ローマ大学名誉学士号、アマルフィ名誉市民他。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
うえぽん
yokkoishotaro
Go Extreme
Go Extreme