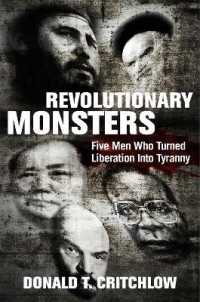出版社内容情報
日本知財学会の10周年記念事業として、知的財産、イノベーション、またそれらの交錯する領域に関する論文を募集。そのうち、テーマ設定、分析視点、また調査分析手法に関して独自性が高く、学術研究の発展に貢献することが期待される14本を厳選し、収録。
第1章 特許制度のモデル化とソフトウェア特許の改善
(吉田哲・久保浩三)
第2章 経済学的手法により検証する存続期間と特許料に関する知財政策の展望
(北田透)
第3章 権利の広さ指標としての格成分数
─実社会への活用に向けて─
(安彦元・安高史朗)
第4章 知識創造性を高めるモチベーション・マネジメントの研究
(金間大介)
第5章 所有から利用へのパラダイムシフトに伴うサービスとデバイスの相互作用
―サービスとデバイスが協働的価値形成を行うための知財マネジメントに関する考察―
(沙魚川久史・小川延浩・妹尾堅一郎)
第6章 知的財産組織の発展モデル及びイノベーション効果の計測手法
―特許と標準の統一的マネジメント―
(田村傑)
第7章 産学間共同研究に関する知財研究の今後の方向性についての考察
(西尾好司)
第8章 アカデミック・ナレッジはイノベーションに貢献しているか?
―ライフサイエンスに基づく製薬・バイオのイノベーション創出に向けて―
(隅藏康一・齋藤裕美)
第9章 材料イノベーションの形成過程の可視化に向けた 特許指標の提案
―リチウムイオン電池の材料開発を事例とした実証分析―
(柴田洋輔)
第10章 医療のためのイノベーション政策の構築に向けて
―科学技術政策と医療制度の整合性をめぐる諸課題―
(齋藤裕美)
第11章 一次産業における知財の活用―地理的表示と地域団体商標の展望―
(香坂玲・西悠)
第12章 水産業における知的財産取得に向けて
(前田敦子・中村宏)
第13章 コンピュータ・ソフトウェアの課税問題
―著作権使用料(所得税法第161条第7号)の課税要件の構築―
(細川健)
第14章 日本の知財教育の進展と日中韓における知財教育交流の展開
(世良清・松岡守・村松浩幸・陳愛華・吉日?拉・錦秀)
()内は執筆者
内容説明
知的財産、イノベーション、ならびにそれらの交錯する領域において、今後重要性が高まる研究課題を展望。特許制度の課題とその分析手法、知財の創出あるいは活用の段階におけるマネジメント、産学連携、特定技術分野のイノベーション、ならびに知財をめぐる新たな課題をテーマとした、14の論文を収録。
目次
特許制度の課題とその分析手法(特許制度のモデル化とソフトウェア特許の改善;経済学的手法により検証する存続期間と特許料に関する知財政策の展望;権利の広さ指標としての格成分数―実社会への活用に向けて)
知財の創出あるいは活用の段階におけるマネジメント(知識創造性を高めるモチベーション・マネジメントの研究;所有から利用へのパラダイムシフトに伴うサービスとデバイスの相互作用―サービスとデバイスが協働的価値形成を行うための知財マネジメントに関する考察;知的財産組織の発展モデル及びイノベーション効果の計測手法―特許と標準の統一的マネジメント)
産学連携(産学間共同研究に関する知財研究の今後の方向性についての考察;アカデミック・ナレッジはイノベーションに貢献しているか?―ライフサイエンスに基づく製薬・バイオのイノベーション創出に向けて)
特定技術分野のイノベーション(材料イノベーションの形成過程の可視化に向けた特許指標の提案―リチウムイオン電池の材料開発を事例とした実証分析;医療のためのイノベーション政策の構築に向けて―科学技術政策と医療制度の整合性をめぐる諸課題)
知財をめぐる新たな課題(一次産業における知財の活用―地理的表示と地域団体商標の展望;水産業における知的財産取得に向けて;コンピュータ・ソフトウェアの課税問題―著作権使用料(所得税法第161条第7号)の課税要件の構築
日本の知財教育の進展と日中韓における知財教育交流の展開…世良清・松岡守・村松浩幸・陳愛華・吉日〓(かつ)拉・錦秀)
-
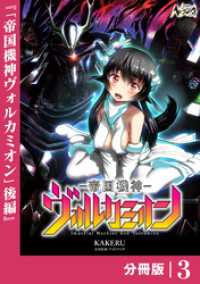
- 電子書籍
- 帝国機神ヴォルカミオン【分冊版】3 ノ…