出版社内容情報
子供の特殊性を配慮した特別なアプローチの方法、教育学・心理学など総合的な知識が必要な分野の概説書。
内容説明
子どもの精神的な「病気」に関する考え方の時代的変遷について記述。成人とは異なり、親や周囲との関わりが大きく影響する「子ども時代」と呼ばれる時期が大きな意味をもつ。子どもの特徴を考慮した特別なアプローチが必要であり、一般精神医学の一領域からは独立した専門科目である。
目次
第1部 歴史(児童精神医学の歴史はどのように記載されてきたか;問題提起)
第2部 児童精神医学は一つのダイナミズムである(本質、実在、そして全体性;児童青年期精神医学の特殊性)
結論 創造の義務
著者等紹介
阿部惠一郎[アベケイイチロウ]
1949年生まれ。早稲田大学仏文科卒業、慶応大学大学院修士課程仏文学専攻中退、東京医科歯科大学医学部卒業。創価大学教育学部教授(臨床心理学専修)、あべクリニック(北海道名寄市)院長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
PukaPuka
2
こういう視点で児童精神医学を考えたことはなかった。2021/11/30
ぼっせぃー
1
『子どもは、失楽園の象徴であり同時に再び見いだされた楽園の象徴であり(略)、素朴で荒々しい衝動を抱え、直截に語り(略)子どもは、われわれ大人の欲望や牧歌的あるいは怪物のような同一化の集積場の中にしか、そしてわれわれ大人が直接に連れて行くことのできない世界との仲介者としてしか存在しない。そこでは、子どもはスポークスマンであり、財布であり、われわれの幻滅の補償であり、滅びることのない仲介者なのである。人間が不完全な動物として生き続けること、人間の未来が続くことを子どもが思い出させてくれる』歴史というより列挙。2023/06/29
Asakura Arata
1
子どもとは何かを問いかけている本。「児童精神科医は心理学教育学を学ぶべきだ」というのは、そうかもしれないが、精神医学さえしっかり学んでいない人もいる現状を見ると、宙に浮いてしまう言葉ではある。2014/06/04
-

- 電子書籍
- ニューノーマル【単行本版】8 コミック…
-
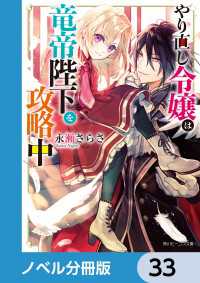
- 電子書籍
- やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中【ノベル…
-

- 電子書籍
- 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭…
-

- 電子書籍
- ことわざ検定 7~10級
-

- 電子書籍
- フリーターが地味に異世界転移するマンガ…




