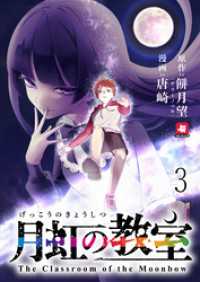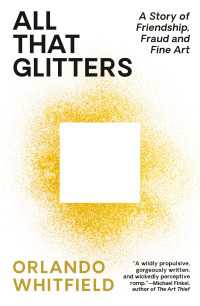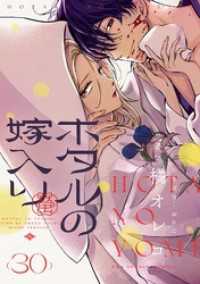内容説明
大聖堂は、文化の精華、キリスト教精神の象徴である。四世紀の創成期から現代にいたるまで、その歴史を解説。建築様式の変遷、社会における役割、管理・運営をする組織、棟梁の仕事ぶり、そこで営まれる暮らしなど、多面的に紹介する。大聖堂の見方を変えさせる一冊。
目次
序 大聖堂とは何か
第1章 西暦一〇〇〇年以前の司教とその教会(司教の権能;どのような建物にするか)
第2章 聖堂参事会、大聖堂の魂(聖堂参事会の成立;神を讃える仕事;教育事業;慈善事業;参事会境内)
第3章 大聖堂の黄金時代(一一四〇~一二八〇年)(隆盛期;聖なる思想家たち;新しい建築術;発展過程と伝播;内部空間;ファサードのメッセージ;建築作業の流れ;資金調達)
第4章 傷ついた大聖堂、再発見された大聖堂(大義をかざす偶像破壊者たちの蛮行;ロマン主義時代の再発見;今日の大聖堂)
著者等紹介
武藤剛史[ムトウタケシ]
1948年生。京都大学大学院博士課程中退。フランス文学専攻。共立女子大学文芸学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hide
11
おもにフランスの大聖堂について、宗教・社会的な機能の変遷、役割変化と技術進歩による建築様式の変遷、参事会や棟梁の暮らしなど様々なトピックを広く紹介しており、ヨーロッパ観光で大聖堂を訪れた際に楽しみが増えそう。/過去の大聖堂はもとは今日よりもきらびやかであったものの、各地の財政難による金属供出、宗教改革期の偶像撤去、フランス革命期の脱宗教化と戦費供出で今日の簡素な内装になったというエピソードが興味深い。神仏分離令と廃仏毀釈により日本の寺社が大きく姿を変えたように、大聖堂も歴史とともに姿を変えてきたのだ。2023/01/12
hajimemasite
3
中世フランスの騎士同様、大聖堂に関し包括的に記述している。ただ、中世フランスの騎士が通史的な部分をバッサリ大雑把に扱っていたのに対し、きちんと扱った為、その他の大聖堂の各役割的な部分が薄くなってしまっているのは残念な部分であった。これも同じく手元にあると便利そうな本。2017/07/08
陽香
2
201001302016/10/18
みそ
0
文庫クセジュ凄すぎ…… どんどんドゥオモの層が厚くなるぜえ。 大学生中にフランスに行きたい、フランス語できる友達を作るか、自分で学ぶか。2011/07/07