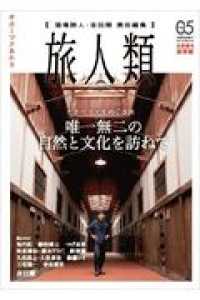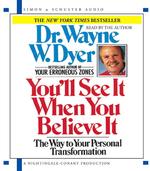内容説明
アダムが食べたのはリンゴではないのに、なぜ原罪のシンボルになったのか、食卓の上のサソリは何を暗示するのか?西洋の文化芸術の理解を助ける五〇〇以上のシンボルを、福音書を中心に聖書全体から集めて、解説する。芸術鑑賞の折のハンドブックとして利用するのも、読み物として通読するのもよしの小事典。
著者等紹介
武藤剛史[ムトウタケシ]
1948年生。京都大学大学院博士課程中退。フランス文学専攻。共立女子大学文芸学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マウリツィウス
14
【キリスト教図像の多義解釈論】新約聖書以降明確化したキリスト教のシンボル案は中世キリスト教美術に受け継がれ、宗教美術としての聖書の世界は絢爛な写本を彩色する。新約/旧約には暗示的表現も含まれることにより、先んじたダンテの魅力的技法はのちにルネサンス絵画へと実体化、文学は本来美術よりも知的読解を要する点で高位な芸術とされ従来聖書の写本様式化を拒んできた。ケルズの書に表現されたラテン時代キリスト教の再現率はむしろ言語芸術に逆導入される。言わずと知れたあの奇書の到来はアイルランドの美的生産世界のみが誕生させた。2013/05/03
マウリツィウス
12
【キリスト図像学】神学的/宗教学的論点から洞察するならば新約聖書がシンボル化した領域とはイコンではなく旧約的偶像を改善と更新を課題とした。「偶像=専有アイテム」を孕む危険性は従来西洋美術史にも存在せず、あるいは根本意味での図像否定を行った宗派ないし教会は厳密には定義し得ない。そして、イコノクラスムとの関連性を吟味すると《美術史》概念はキリスト信仰との連環において既に福音書に存在記述があり、「見ずに信じる者」とは「音楽芸術」だけではない記録とテモテ書簡による明晰な偶像定義が感謝と敬虔とを以て美術史を再定義。2013/06/11
へんかんへん
4
掛け算ができなくなってることに気づいたつらい2017/03/19
植岡藍
3
キリスト教以外にも西洋芸術理解に役立つ一冊。図版はないけど逆に頭の中で検索したりイメージが膨らんでよかった。聖書の一般的な解釈を知るにもちょうどいい。2018/11/13
せびたん
1
聖書の理解の助けになるかと思ったけど、キリスト教徒でない私が聖書を読むのは不眠な夜に限られている上、この本を買った頃からなぜか不眠な夜を迎えることがなくなったので、ほぼ映画鑑賞の手引きとして利用しております。 「なぜこのシーンで蛙が出てくるのか?🐸」というような疑問が生まれたときに本書で調べますと、おもしろい解釈が可能になることがあり重宝してます。
-

- 電子書籍
- 腹黒社長にハメられました【タテヨミ】第…
-
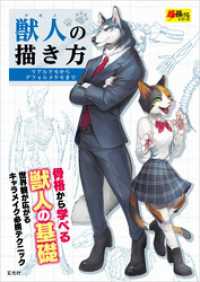
- 電子書籍
- 獣人の描き方