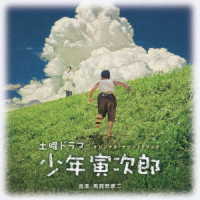出版社内容情報
東独、ポーランド、ハンガリーにおいて、ソ連はいかに勢力圏を確立したのか? 『グラーグ』(ピュリツァー賞受賞)の歴史家による決定版!
内容説明
「冷戦終結三十年」にして明かされる、東欧を支配した「全体主義」の実態。東独、ポーランド、ハンガリーにおいて、ソ連はいかに勢力圏を確立したのか?ピュリツァー賞受賞の歴史家が、最新研究に基づいて、「スターリン主義」の真相を暴く!全米図書賞最終候補作品。
目次
第1部 偽りの夜明け(ゼロ・アワー;勝者たち;共産主義者たち;警察官;暴力;民族浄化;青年;ラジオ;政治;経済)
著者等紹介
アプルボーム,アン[アプルボーム,アン] [Applebaum,Anne]
1964年生まれ。米国出身の歴史家、ジャーナリスト。『ワシントン・ポスト』のコラムニスト。『グラーグソ連集中収容所の歴史』(白水社)でピュリツァー賞受賞。『鉄のカーテン―東欧の壊滅1944‐56』で全米図書賞の最終候補、クンディル歴史賞受賞
山崎博康[ヤマザキヒロヤス]
1948年、千葉県生まれ。東京外国語大学卒業、共同通信社入社。ワルシャワ支局長、モスクワ支局長を歴任。現在、共同通信社客員論説委員。法政大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TK39
3
第二次世界大戦後の国境の変更、ドイツ人、ポーランド人の民族追放、移動がどのように行われたか、弱小政党であった共産党が治安組織を握り、徐々にソビエト式の共産主義体制を築いたかを詳しく書いている。かなり詳細に記述しているところもあり、多少疲れる。 2019/05/06
あらい/にったのひと
2
ちょっと時間かけすぎたかな。共産圏の話としてかなりおもしろい。誰が読んでも面白いのは終盤にあるインフレの話か。とはいえこの環境下で生きることを強いられていた人たちが実在するのを考えると、あんまり笑ってばかりもいられないなあ、というのを最近考えます。2020/03/16
まつだ
1
1939年のソ連ポーランド侵攻から始まる「東欧」共産党支配のルポ。事実であることに気が重くなる。批判を許さない組織ってのは、きっかけまちなんだな。2020/03/29
渡邉駄作
0
意外と東欧における戦後政策の本は初めて読んだ。聞きしに勝るソ連軍の酷さは言うに及ばず、小スターリンたちの民主的政策の滅茶苦茶さはほとんどディストピア小説。東ドイツ、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランドの共産化が上巻の内容でユーゴはともかく、アルバニアやらブルガリアはどうなっていたのか気になった。かなり滅入る内容ではありますが、頑張って下巻へ。2019/06/04
Oltmk
0
コミンテルン・政治・警察・メディアなどのキーワードを通じて、戦間期から戦後の東欧を描写し如何に共産圏となる道を辿り、鉄のカーテンが敷かれたかを描写する専門書。今まで注目されていなかった戦後のドイツ人やドイツ系住民に対する強制移住により共産国家としての布石を築いていった、敗戦した選挙に対して他政党を徹底的に弾圧して一党独裁への道を辿って行ったどのように東欧が共産国家となったのかを飛躍する事なく描写できている。戦間期から戦後の共産圏となった東欧に知りたい人に対しては精神的にキツイ話題が入っている事に注意。2019/04/17
-
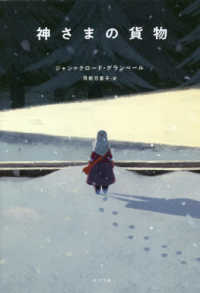
- 和書
- 神さまの貨物