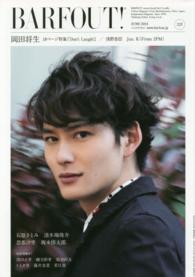出版社内容情報
ともに生きる、新たな方法
東日本大震災以降、以前にも増して「コモンズ」という言葉を聞く機会が増えてきた。人口が減少し低成長を余儀なくする時代に、なぜこの概念が脚光を浴びることになったのか? 日本の社会科学を牽引する論客が回答を与えようとしたのが本書である。
「コモンズ」が人口に膾炙するきっかけとなったのは、ギャレット・ハーディンの「コモンズ(共有地)の悲劇」論文(1968年)だった。
本書では、1990年代に流行った「公共性」論、さらにはリベラリズム・コミュニタリアニズム・リバタリアニズムといった思潮を再考しながら、この概念を彫琢するとともに、いかなる場でこの概念が有効か検証していく。
大正日本の「社会」への眼差し、まちおこしが大きな課題となっている商店街、持ち家社会で周縁化した戦後日本の公営住宅、豊かさから取り残されたカナダのインディアン保留地、利益分配が出来なくなった政党、時空を超越する宇宙・サイバー空間、移民危機に揺れる欧州国民国家──。
そこで浮かび上がってくるのは、「公」か「私」かではなく、「公」と「私」をいかに媒介する論理を見つけだすかである。これまでの公共性論の視界に入らなかったものは何なのか? 2020年代の「公私」論の決定版。
待鳥 聡史[マチドリ サトシ]
著・文・その他/編集
宇野 重規[ウノ シゲキ]
著・文・その他/編集
内容説明
ともに生きる、新たな方法。ポスト2020年の社会を考えるために。
目次
対談 いま、なぜ、モコンズか?前篇
1 歴史のなかのコモンズ(コモンズ概念は使えるか―起源から現代的用法;近代日本における「共有地」問題)
2 空間のなかのコモンズ(衰退する地方都市とコモンズ―北海道小樽市を事例として;コモンズとしての住宅は可能だったか―一九七〇年代初頭の公的賃貸住宅をめぐる議論の検証;保留地というコモンズの苦悩)
対談 いま、なぜ、コモンズか?後篇
3 制度のなかのコモンズ(コモンズとしての政党―新たな可能性の探究;脱領域的コモンズに社会的コモンズは構築できるか;ミートボールと立憲主義―移民/難民という観点からのコモンズ)
著者等紹介
待鳥聡史[マチドリサトシ]
1971年生まれ。京都大学大学院法学研究科博士後期課程退学。博士(法学)。現在、京都大学大学院法学研究科教授。『財政再建と民主主義』(有斐閣)でアメリカ学会清水博賞、『首相政治の制度分析』(千倉書房)でサントリー学芸賞
宇野重規[ウノシゲキ]
1967年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。現在、東京大学社会科学研究所教授。同研究所で“希望学”プロジェクトをリードしたほか、『政治哲学へ』(東京大学出版会)で渋沢・クローデル賞、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ)でサントリー学芸賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひつまぶし
うーひー
Atsumi_SAKURADA
takao
akio numazawa