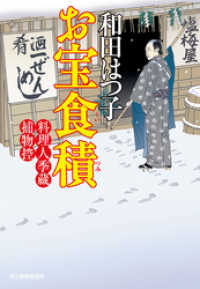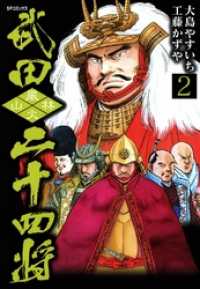出版社内容情報
本が一点物だった時代、本の書写、テキストの制作、パトロンによる発注は、どのような意味をもっていたのか。印刷以前の書籍文化誌。
内容説明
写本製作にあたり注文主が、作者が、書記が、各種職人が果たした役割や、できあがった写本がもった政治的意味、さらに傑作「マネッセ写本」を生み出した文芸マネージメントまで、写本をめぐる文化活動をわかりやすく解説する。
目次
第1章 本ができあがるまで(材料の調達;書く・描く;写本製作の場;書記;本の外見;写本の値段;保管とアーカイブ化;印刷術という革命)
第2章 注文製作(文学の中心地;文学愛好家とパトロン;文学マネージメント―マネッセ写本;愛書家―ある十五世紀貴族の図書室)
第3章 本と読者(聞く・読む;身体としての本;五感と読書)
第4章 作者とテキスト(詩人―匿名・自己演出・歴史性;作品―伝承・言語・文学概念)
著者等紹介
ブリンカー・フォン・デア・ハイデ,クラウディア[ブリンカーフォンデアハイデ,クラウディア] [Brinker‐von der Heyde,Claudia]
1950年生まれ。2000年よりカッセル大学教授、2009年より副学長を務める。専門は中世からバロックまでのドイツ文学、特に中世から初期近世における本および図書館の文化
一條麻美子[イチジョウマミコ]
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授(中世ドイツ文学・表象文化論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
71
ヨーロッパの写本について詳しく書かれ白黒だが貴重な図版も掲載されている。専門的なことは分かりませんが本に対する見方が興味深い。即ち:文学、知識、記憶が人間の存在とまだ強く結びついていた社会では、身体性を欠いた文字はほとんど考えられなかった。とあり、1340年頃の本『イタリアの客人』では:ドイツでイタリアの客人を丁重に迎え入れよ。と書かれ、客人として迎えてほしいのは彼自身ではなく彼の本。彼は自分の代わりに本を送り出し、このよそ者が彼の紹介状のおかげで温かく迎え入れられることを願う。父が息子にするように…。と2018/11/09
syaori
67
中世のメディア革命「口承から書記への転換」を、ドイツ語圏の写本から見てゆく本。紙やインク、標準的で読みやすい書体など書記の材料、宮廷や都市の発達による情報伝達メディアとしての役割の確立、注文主と詩人の関係や、既にある物語に「新たな側面を付与する」という近代とは異なる創作意識など様々な面から中世の文学世界の様相が示され興味が尽きません。カール大帝のローマ皇帝位獲得を機に書き言葉としてのフランク語(ドイツ語)が聖なる言葉(ラテン語やヘブライ語)と肩を並べるものとして成立した過程を辿る部分に特に心惹かれました。2023/09/22
刳森伸一
10
写本という観点から中世文学の世界を考察する。当時重要だったのは作者のオリジナリティが光る題材や物語ではなく、古くからある題材をその本質を露わにするように改変することだと説く。そのため写本は(聖なる書物である聖書を除いて)原本をコピーしただけのものではなく、新たな価値を創出する操作でもあった。つまり写本は大量生産される現在の本とは違い、一冊一冊が別の価値を持った作品でもある。私のような凡人には、せいぜいその中の一つを邦訳で享受するしかないわけだが、実際にはもっと豊潤な世界があるのだ。2017/09/12
hika
8
一文字一文字を羊皮紙に写し取りつくられる「写本」。本書では、羊皮紙の製作過程、職人の生活史、そして受注生産で造られ、そして手で写される課程で、書かれた内容(コンテンツ)が微妙に、あるいは大胆に替わっていくそしてそれを語り、歌った詩人たちによる中世文学の多様な世界が語られる。2017/12/30
人生ゴルディアス
4
当時の本の体裁から作り方、原材料、書き手とパトロン関係などの現物的な説明から、当時においてなにかが物語られるということの文化的な話まで。写本制作の際に書き間違いやらによって、異なる版が複数存在するという話は知っていたが、そもそも当時は新しい物語を創作するのではなく、古いことを新たに書き直すことに主眼があったので、「オリジナル」という概念そのものがそぐわないのではないか、という指摘は新しかった。つまり、内容の異同は本当に書き間違いやらが原因なの?と。写本はコピーではなく原本の注釈と見るべきではという指摘。2021/04/21


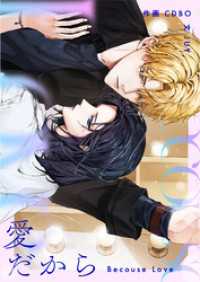
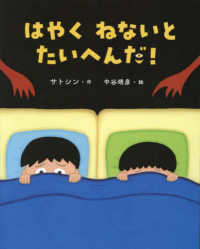
![IT用語図鑑[エンジニア編] - 開発・Web制作で知っておきたい頻出キーワード25](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47981/4798169102.jpg)