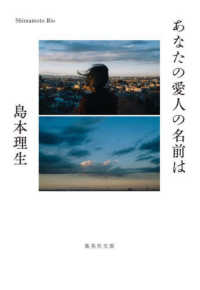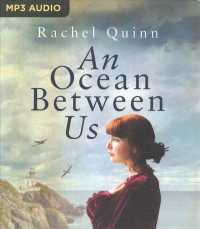出版社内容情報
消える大学と生き残る大学の違いとは何か? 定員割れが起きるメカニズムに着目し、その歴史的経緯にまでさかのぼって検証する。弱小私大淘汰のメカニズムを明快に示す
限界大学――恒常的な定員割れを引き起こし、人材的にも財力的にも大学を経営するだけの能力に欠ける、文字どおり弱くて小規模な弱小私大を、本書ではそう名づけた。
しばらく横ばいだった18歳人口が再び減少傾向に入る2018年以降、私立大学の定員割れが加速し、経営困難校の公立移管や統合、閉校が相次ぐのは避けられないと見られている。本書は、戦後の教育行政の変遷や生徒を送り出す高校側の事情などを踏まえたうえで、統計データを駆使しながら、弱小私大のさらなる弱体化の背景と、定員割れの実態、そのメカニズムを明らかにしていく。
18歳人口の再減少が目前に迫るなか、市場主義的な競争原理が導入され、いま「負け組」増加の条件が整いつつある。その結果もし大学が破綻したら、周囲に及ぼす影響は当の学生や教職員だけにとどまらない。本書には、そうした限界大学への道を避けるべく、組織改革や財務健全化に取り組み、成功した事例も紹介されている。教育行政学・教育社会学の蓄積による実証性と、高校・大学教育に長年携わってきた著者の経験が融合し、説得力に富んだ画期的書。オクスフォード大学教授(教育社会学)苅谷剛彦氏推薦!
小川 洋[オガワ ヨウ]
1948年東京生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、埼玉県立高校教諭(社会科・地歴科)として勤務。並行して国立教育研究所(現・国立教育政策研究所)研究協力者として日本の高校教育とアメリカやカナダの中等教育との比較をテーマに研究。その後、私立大学に移り、教職課程担当の教員として十数年勤務した。主要著書に『なぜ公立高校はダメになったのか』(亜紀書房、2000年)が、共訳書に『ロッキーの麓の学校から――第二次世界大戦中の日系カナダ人収容所の学校教育』(東信堂、2011年)などがある。
内容説明
弱小私大が淘汰されるメカニズムを、統計データを駆使しながら明快に示した画期的書!
目次
第1章 試練に立たされる弱小私大
第2章 どのような大学が定員割れしているか
第3章 混乱の「ゴールデンセブン」とその後
第4章 短期大学とは何か
第5章 短大以上・大学未満
第6章 新たな大学像
第7章 弱小私大と高校
第8章 弱小私大の生き残る条件
第9章 「限界大学」の明日
著者等紹介
小川洋[オガワヨウ]
1948年東京生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、埼玉県立高校教諭(社会科・地歴科)として勤務。並行して国立教育研究所(現・国立教育政策研究所)研究協力者として日本の高校教育とアメリカやカナダの中等教育との比較をテーマに研究。その後、私立大学に移り、教職課程担当の教員として十数年勤務した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハイランド
1.3manen
mazda
けんとまん1007
kotte
-

- 洋書電子書籍
-
土壌のふるまいの基礎(第4版)
…
-

- 電子書籍
- 長門有希ちゃんの消失【分冊版】 46 …