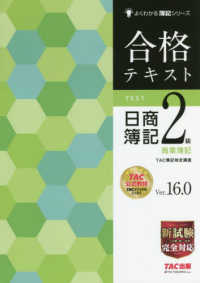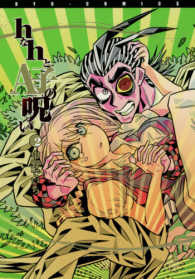出版社内容情報
「名将」の光と影、実像に迫る評伝。英国陸軍少将の著者が新史料や私文書を渉猟し、栄光と挫折の生涯を精彩に描く。地図・写真収録。「名将」の栄光と挫折の生涯を描く評伝
マンシュタインは第二次世界大戦のドイツ軍の「名将」として知られる。名家に生まれ、第一次世界大戦に従軍し、やがて参謀将校として頭角を現し、エリート街道を進む。ヒトラーが権力を掌握し、彼に仕えてフランスを電撃的に打ち破り、降伏に追いやる。独ソ戦ではレニングラードに猛進、またセヴァストポリを陥落させるなど、多大なる戦果をあげる。しかしマンシュタインは、スターリングラードを死守せよとするヒトラーと対立し、解任される。失意のマンシュタインは、戦後、戦犯裁判の訴追という窮境に追い込まれる。マンシュタインは指揮下の部隊が戦争犯罪を行うのを止めず、責任を問われたのだ。すべての訴因について有罪ではなかったものの、禁錮刑に処せられる……。
英陸軍少将の著者は、戦後、称賛と非難の両極端に分かれたマンシュタイン評価に対し、その生涯を包括的に再構成し、ドイツ近現代史の流れを投影しつつ、ドイツの興亡を活写する。マンシュタインはナチ犯罪・戦争犯罪にどこまで関与したのか? 新史料や私文書を駆使し、「名将」の光と影、実像に迫る評伝の決定版。
マンゴウ・メルヴィン[メルヴィン]
英国陸軍の軍人として要職を歴任。2009年には専門家として旧ユーゴスラヴィア国際戦犯裁判に出廷した。2011年に退役、最終階級は少将で、バス勲章と大英帝国勲章を受けている。生粋の職業軍人である著者がドイツ軍事史に関心を抱いたのは在独英軍勤務時代で、なかんずく第二次世界大戦屈指の作戦家であるマンシュタインに注目、伝記執筆を志した。その史資料の博捜ぶりは徹底したもので、ドイツ連邦国防軍の高級将校とのあいだにつちかった信頼関係に基づき、関係者へのインタビューも試みている。
大木 毅[オオキ タケシ]
軍事史研究者、ドイツ近現代史専攻。主要著書に『ドイツ軍事史』(作品社、2016年)、主要訳書にフリーザー『電撃戦という幻 上・下』(中央公論新社, 2003年)、キーガン他『戦いの世界史: 一万年の軍人たち』(原書房, 2014年)がある。
内容説明
ナチ犯罪・戦争犯罪にどこまで関与したのか?スターリングラード包囲戦から、ヒトラーによる解任、敗戦と戦犯裁判まで、英国陸軍少将の著者が新史料や私文書を渉猟し、その栄光と挫折の生涯を精彩に描く。「訳者解説」、人名索引・年譜、カラー口絵地図・写真多数収録。
目次
第11章 スターリングラードへの虚しき戦い
第12章 かいま見た勝利
第13章 クルスクの敗北
第14章 二正面の闘争
第15章 最後の闘争
第16章 罪と罰
著者等紹介
メルヴィン,マンゴウ[メルヴィン,マンゴウ] [Melvin,Mungo]
英国陸軍の軍人で、サンドハースト陸軍士官学校ならびにケンブリッジ大学ダウニング・カレッジで学び、また、軍人となってからは、ドイツ連邦国防軍指揮幕僚大学校に派遣されて入校し、その教育も受けている。1974年に任官、王立工兵隊に入隊して以来、陸軍でキャリアを重ね、さまざまなポストに就いてきた。主立ったものとしては、第二八工兵連隊長、陸軍戦略・戦闘研究所長、NATO(北大西洋条約機構)連合軍即応兵団工兵隊長、参謀本部陸戦監、国防省作戦能力監督部長、在独英軍給養司令官などが挙げられ、要職を歴任してきた
大木毅[オオキタケシ]
1961年東京生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学。DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生としてボン大学に留学。千葉大学その他の講師を経て、現在著述業。二〇一六年度より陸上自衛隊幹部学校部外講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
ジュン
代理
A.Sakurai
ソノダケン
-
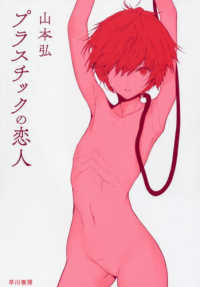
- 和書
- プラスチックの恋人