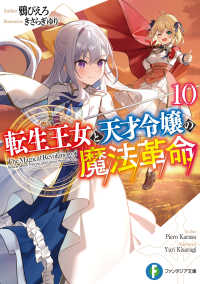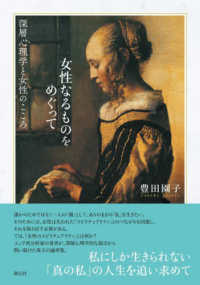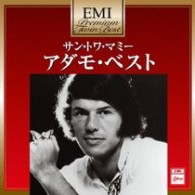出版社内容情報
言葉を発せず、歩くのをやめられない少女。包囲下で爆撃にさらされ、地下室に拘束されたまま、見知らぬ「あなた」に宛てて書き綴る。
内容説明
私の言葉を読んでいるとき、きっと、私はあなたと一緒にいますよ。言葉を発せず、歩き出すと足が止まらなくなる少女リーマー。包囲下で爆撃にさらされ、地下室に拘束されたまま、一本きりの青いペンで、見知らぬ「あなた」に宛てて書き綴る。2018年度フェミナ賞外国文学部門・2021年度全米図書賞翻訳部門最終候補作。
著者等紹介
ヤズベク,サマル[ヤズベク,サマル] [Yazbek,Samar]
1970年、シリア・ラタキア県ジャブラ生まれ。99年、短篇集『秋の花束』を刊行、文筆生活に入る。アサド大統領と同じくイスラーム教アラウィー派の一族の出身でありながら、2011年以降、一貫して反アサド政権の立場をとり、逮捕・拘束を経て同年夏にシリアを脱出。小説家、シナリオライター、編集者、ジャーナリストとして活躍する一方、女性を支援するNPO団体を設立。2009年、39歳以下の優れたアラブ作家「ベイルート39」の一人に選ばれる。2011年に始まったシリア蜂起の最初の四か月の日記に基づく長篇小説『交戦』を2012年に刊行。英訳は同年の国際ペンクラブのピンター文学賞「勇気ある国際的作家」を受賞した
柳谷あゆみ[ヤナギヤアユミ]
慶應義塾大学文学研究科後期博士課程単位取得退学。早稲田大学、慶應義塾大学などで非常勤講師(アラビア語担当)。歌人として第一歌集『ダマスカスへ行く 前・後・途中』(2012年)で第五回日本短歌協会賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
ヘラジカ
ねむ
星落秋風五丈原
taku