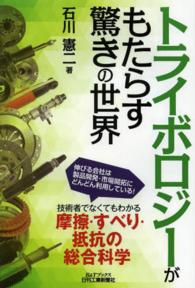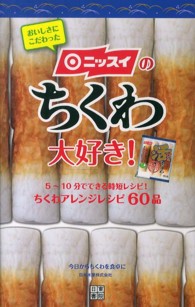内容説明
田舎道。一本の木。夕暮れ。エストラゴンとヴラジーミルという二人組のホームレスが、救済者・ゴドーを待ちながら、ひまつぶしに興じている―。「不条理演劇」の代名詞にして最高傑作。
著者等紹介
安堂信也[アンドウシンヤ]
1927‐2000年。現代フランス演出史専攻。早稲田大学名誉教授
高橋康也[タカハシヤスナリ]
1932‐2002年。イギリス文学(特にシェイクスピアおよび現代劇)専攻。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
221
初演時の役者はいずれも知らない人たちだが、今、自分がプロデュースするとすれば、主演の二人にはやはり初老の喜劇役者を使うだろう。バイプレイヤーとして長年舞台をつとめてきた、ペーソスのあるような役者がいい。一方、戯曲としてこれを読むと、読後は強い寂寥感に襲われることになる。あたかも胸腔全体が空洞になったかのような。悲しみに似た感情は、1幕の終り近くが最も高くなる。そこで終わってもいいようにも思う。しかし、再び同じような情景と対話が繰り返される2幕の存在こそが、この劇が「不条理劇」と冠される所以なのだろう。2013/02/10
長谷川透
32
「不条理演劇」と帯書きにはあるが、気構えて読むことなんてない、この戯曲は喜劇として腹を抱えながら読めるではないか。ゴドーを待つ二人の浮浪者。しかし彼らはゴドーの容貌さえ知らず、彼を待つ尤もらしい理由を読者(観客)は掴めないまま物語はゆるやかに進む(時間というものの輪郭がぼやけてくるようだ)。ゴドーは存在するのかさえわからない。ゴドー=神という説を受け入れてしまえば解釈は容易い。しかし、解釈云々よりも、待つ対象の不在の元で繰り返される人間喜劇をただただ楽しめばそれでいいのではないかと僕は思う。2012/09/29
榊原 香織
28
2時間の舞台だそうで、観るとまた印象が変わるのだろうけど。 短いセリフに深い意味があるらしく、注を読まないと全くわからない。 主人公二人は死んでるんではなく?2020/09/29
zirou1984
28
戯曲『ゴドーは待たれながら』鑑賞ついでに再読。「いつ来るの?今でしょ!」とばかりにやって来るはずのゴドーを2日間待ち続ける話なのだが、最後まで来ることはなく舞台は終わる。そもそもの所、キリスト教は彼の到来を2000年も待ち続けているのだから2日など今更何の事はない。必要とすべき理由は剥ぎ取られ、もはやゴドーは到来しないことによって表現となり実存を確認する手段となる。思弁と言語は空回りし続け、身体表現や沈黙こそが主役の様だ。もしくは、ゴドーとは舞台の上映であり演者は演者を演じている楽屋ネタと見るのも一興か。2013/04/25
三柴ゆよし
27
どこでもない場所でひとりの男を待ち続ける話。解釈の数はほとんど無限に存在するが、作中人物であるウラジーミルとエストラゴンのふたりは、「待ち人来ず」というある種の極限状況に追い詰められながらも、その現状をなんとか耐えうるものにしようと四苦八苦する。暇つぶしに首でも吊ろうかという発想はすごいよね。その悪戦苦闘ぶりがスラップスティック喜劇としての様相を呈してくるため、読んでいて辛さを感じることは不思議とない。ブッツァーティにベケットやカフカのユーモアがあれば、あの作品もまた違った味わいになっていたのだろう。2013/04/10