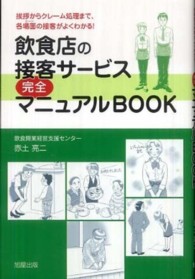内容説明
喪失の世界を生き延びるために―パリ、京都、東京、神戸。これら四都市をめぐり、三人の日本人―小林一茶、夏目漱石、写真家山端庸介の人生に寄り添いつつ、喪失・記憶・創作について真摯に綴った“私”小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chantal(シャンタール)
61
フランスの学者が一茶、漱石、山端庸介(原爆投下直後の長崎で軍の命令により撮影を行った写真家)を語る。その合間にパリ、京都、東京、神戸で暮らす彼の物語が挟まれる。彼の物語にはパリから逃げるように日本へやって来た彼の痛みや苦しみが漂う。語りは全体的にモノトーンで不穏な空気を纒う。最後の章でなぜ語られたのが一茶達だったのかがわかった時、彼の慟哭を突如理解し胸が苦しくなる。彼が日本へ逃げて来たのは必然だったと思わされる。こここそが還る場所だったのか。「さりながら」人は生きて行かねばならぬ。白水社、良い本を作る。2024/07/05
ねこさん
28
痛みが、視神経に絡みついて癒着している。意識が倦怠に捕らえられて、もつれを探り当てることができない。脈拍と吐気そのものに身心が作りかえられる。めくれ上げられたように剥き出しの世界、その表面を打つ雨音、暗闇の中で形象を浮かび上がる。そのヴォリュームが内側から接近する。一茶、漱石、わが子を失った身体から眺められた風景、代替可能性が延々と続く風景。形を持った世界と形の無い世界がシームレスに溶けているのを眺め、変化の兆しへと緩やかに注意を払う。感情を生じさせることのないよう、静かに生きることが義務づけられている。2018/07/28
踊る猫
27
このようにしか書けない作家なのは『永遠の子ども』を読んでわかっていたつもりだったが、ここまで切実に自分の中で揺れる情動と向き合うのは難しいことだろう。オリエンタリズムに陥ることを恐れず、著者は自分の目から見た一茶や漱石、山端庸介やその他の「日本的なもの」を語る。著者の無常観と日本の持つ「もののあわれ」な側面がシンクロした結果(つまり、出会うべくして出会ったものが奇蹟的に融合し)、このような美しい書物となったことを喜びたい。だが、この出会いはこの書き手を癒やすものだろうか。高すぎる知性故の苦悩が滲み出る本だ2021/01/13
踊る猫
26
乏しい私の読書から連想させられたのはリルケやポール・オースターの散文だった。前者とは死に愚直に対峙しているという意味で共通していると思われるし、後者とは子どもの死(それは自分の死よりもある意味では辛いことだろう)を考えてそこから逃げていないところが似ていると思ったのだ。清潔感のある上品な訳文から伝わるのは、日本を決して過度に賛美することなく、しかし妙なフランス人としてのナショナリズムも捨ててフェアに眺めようとする、これもまたナイーヴな思考/知性のあり方だ。個人的に苦悩していた時に読んだので、ヒントはあった2019/12/14
松本直哉
25
まんなかあたりにある、旅先から帰ってみると洗面所の鏡が落ちて砕けていたエピソードが印象に残る。取り返しのつかない喪失。拾い上げたかけらで血を流す。壁に残された空虚な窓のような鏡のあと。幼い子を亡くした小林一茶と夏目漱石、原爆後の長崎で瀕死の子に乳を含ませる母親の写真についての文章の間に、自らの子を喪った体験が、日本の私小説と見まがうほどの個人的なことばで点綴されてゆく。その個別性と、一茶や漱石を論じるときの犀利な批評性が奇妙にないまぜになる。砕けた鏡のかけらに触るようにつらい思い出に触れて血を流す心。2017/10/09