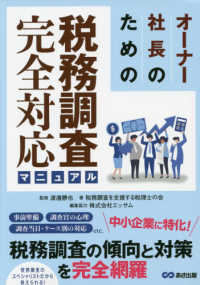出版社内容情報
モロッコの港町を舞台に、若い娘ファトマの眼差しをめぐって交錯する欲望の数々。詩的で官能的な文学世界。
【著者紹介】
1951年メキシコシティ生まれ。小説家、詩人、批評家。パリ第七大学でロラン・バルトの指導を受け、80年博士号を取得。1987年に発表された本書で、メキシコの最も重要な文学賞のひとつ《ハビエル・ビジャウルティア賞》を受賞。
内容説明
北アフリカの港町モガドールで若い娘ファトマが投げかける謎めいた眼差し、町の人々のあいだで交錯する生と性の予感…。メキシコで最も権威ある文学賞「ハビエル・ビジャウルティア賞」受賞作。
著者等紹介
ルイ=サンチェス,アルベルト[ルイサンチェス,アルベルト][Ruy S´anchez,Alberto]
1951年メキシコシティ生まれ。小説家、詩人、批評家。75年よりパリで学び、80年にパリ第七大学より博士号取得。82年に帰国。88年以来、美術雑誌「アルテス・デ・メヒコ」の主筆を務める。1987年に発表した『空気の名前』で、メキシコの最も権威ある文学賞「ハビエル・ビジャウルティア賞」を受賞。2000年、フランス政府より芸術文化勲章(オフィシエ)を授与される
斎藤文子[サイトウアヤコ]
1956年生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業。米国ライス大学大学院修士課程修了。東京大学大学院教授(地域文化研究専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
46
モロッコの港町で海を眺める少女、ファトマ。子供だった彼女がとらえどころもない大人の色香と美しさを纏わせるようになったのは、ハマーム(公衆浴場)で出会った女人、カディアに恋をしたからだ。湯気で煙る浴場に濡れそぼる女体と息が交じり合う熱さ、身体が放つ芳香などの描写がなんとも官能的。それに感応してファトマが自分の欲情を自覚する時の戸惑いの瑞々しさと揺れに対し、ファトマに対する即物的で淫らな妄想を逞しくさせる男達の滑稽さよ。2017/01/07
長谷川透
26
架空の共同体を舞台にした小説には二つの系譜があるように思う。一つはヨクナパトーファ・サーガで『百年の孤独』のマコンドもこの系譜に含まれる。共同体は作者の所有物としてあり、その中で繰り広げられる物語は天蓋からの眼差しによって語られる。『空気の名前』もまた架空の都市を舞台にした小説であるが、こちらは『ペドロ・パラモ』のコマラの系譜にある。コマラが死者の声の集合体ならば、モガドールは欲望のだだ漏れの集合体である。同じ系譜にありながら死と生(に纏わりつく欲望)という対極関係にある両作品を読み比べても面白いと思う。2013/07/13
すけきよ
20
ハンマームが重要な舞台になっていることもあるのか、文章からは非常に濃密な湿度と漂う香料が感じられる。物語も筋道があるようなないような、ラストもあるようなないような……だからこそ、謎めいたファトマの視線が案内役となって、より街の情景が浮かび上がってくる。また、人々の噂で息づく街は、呼吸する肉体のようでも、女体をなぞっているかのようでもあり、エロティックなイメージが喚起される。「物語」の物語でもあって、それらは語られることのよっても、語られないことによっても、新たな物語が生み出されていく。2013/02/24
きゅー
18
モロッコのとある港町。17歳の少女ファトマは窓辺に佇み、じっと水平線を見つめ続ける。物語らしい物語は何も起きない。ファトマに寄り添い彼女の眺める海をともに眺め、彼女の不安と官能に共感し、過去に起きた出来事をなぞらえる。彼女が愛する人や、彼女を愛する人達の内なる言葉が記されるが、それらは一見した限りでは凪いでいる海のように多くの感情を孕んでいる。日々の断片がモザイクのように記され、ファトマは水平線の向こうにあって見ることのできない、得ることのできない何かに心奪われ、花開きつつある感覚の泉に泳いでいる。2016/03/02
鷹図
17
メキシコ人の作者によって書かれた、北アフリカにあるイスラム文化圏の港町、「モガドール」。聞き慣れない名前のこの町は、「ヨクナパトーファ」や「四国の森」のように、作品世界によって生成されるトポスとしての港町、なのだと思う。話しの筋はあってないようなもの。町に住む美少女の、海へ向けられる物憂げな眼差し。その視線の先と意味をめぐる、町の人々の憶測と思惑の物語。イスラム批判ともとれる箇所がいくつかあるが、文章は散文詩的で、どことなくキニャールの緒作を想起させる。正直好みな作風ではないけれど、独特の雰囲気があった。2013/03/25
-
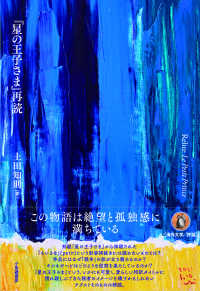
- 和書
- 『星の王子さま』再読