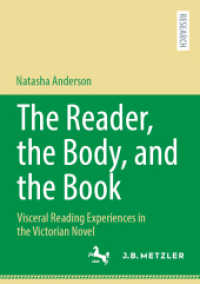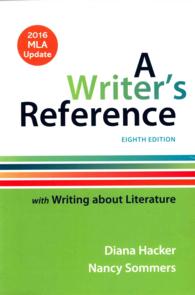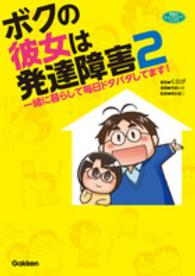出版社内容情報
大江健三郎作品の装幀を手がけ、同時代を伴走してきた著者が、六〇年代の大江文学と向き合い、現代への鮮烈なメッセージを?み取る!
装幀を手がけた大江健三郎作品の秘密
大佛次郎賞を受賞した『本の魔法』では、実は著者と最も関係が深いと思われる大江健三郎について言及されていなかった。370頁を超える本書に目を通せば、読者はその理由がわかるだろう。
著者が手がけた装幀で、最多を誇るのが大江の作品である。二人はほぼ同世代。大江10歳、著者9歳のときに敗戦を経験し、同時代を歩んできた。1970年に『叫び声』の装幀を依頼されて大江と出会い、以来、作品の深い読みが反映された装幀で大江の代表作が次々と世に送り出された。
大江作品は、小松川高校事件(女子高生殺害事件)、安保闘争、浅間山荘事件、狭山事件、原爆と原発事故による被曝、沖縄、在日朝鮮人の問題など、常に実際の事件や社会問題と想像力が結びついたものである。本書で大きく取り上げる『叫び声』と『河馬に?まれる』には、大江が追究してきたテーマの全てが網羅され、不気味なほど現代に繋がる。
著者は装幀をした時代を振り返り、大江作品を改めて多方面から精読し、国家や組織などと対峙する「個人」の魂の声に突き動かされながら、小説からだけではわからなかった事実を引き出していく。著者ならではの視点と感性で大江文学から現代への鮮烈なメッセージを?み取る、渾身の書き下ろし!
序章 一冊の本の形
第一章 『叫び声』
一 こらあじゅ1987
二 恐怖の時代
三 黄金の青春の時と犯罪
四 停滞から抜け出す少年
五 ジラード事件
六 レモン湯を飲みながら
七 わが耳を疑うもの
八 幸福をさずける家
九 巨大な無線劇場
一〇 忘れておいたほうがつごうのよい問題
一一 「怪物」の本質について
第二章 『河馬に?まれる』
一 ひとしれず微笑む
二 熱狂
三 パラダイス
四 少年A
五 無意味な死
六 『洪水はわが魂に及び』
七 大石芳野の写真
八 エリオットの詩からの河馬
九 幼児虐待
一〇 闘争と青春
一一 「原爆の図」美術館
一二 「ほそみさん」の手紙
一三 革命女性
終章 小説の方法
あとがき
大江健三郎著作装幀一覧
参考文献
【著者紹介】
画家・作家。1936年、群馬県前橋市生まれ。1988年「バー螺旋のホステス笑子の周辺」で芥川賞候補、93年「犬」で川端康成文学賞、2007年『ブロンズの地中海』(集英社)で毎日出版芸術賞、11年『本の魔法』(白水社)で大佛次郎賞受賞。著書はほかに『紅水仙』(講談社)、『戦争と美術』(岩波新書)、『影について』(講談社文芸文庫)、『戦争と美術と人間』(白水社)、『孫文の机』(白水社)、『絵本の魔法』(白水社)、『幽霊さん』(ぷねうま舎)、『雁の童子』(作・宮澤賢治、絵・司修、偕成社)、『絵本 銀河鉄道の夜』(作・宮澤賢治、絵・司修、偕成社)など多数。1986年、池田二十世紀美術館で「司修の世界展」、2011年、群馬県立美術館で「司修のえものがたり―絵本原画の世界―展」を開催。
内容説明
大江健三郎作品の装幀者は、はからずも同時代を併走してきた。大江文学から読み解く現代への鮮烈なメッセージ!
目次
序章 一冊の本の形
第1章 『叫び声』(こらあじゅ1987;恐怖の時代;黄金の青春の時と犯罪;停滞から抜け出す少年;ジラード事件 ほか)
第2章 『河馬に噛まれる』(ひとしれず微笑む;熱狂;パラダイス;少年A;無意味な死 ほか)
終章 小説の方法
著者等紹介
司修[ツカサオサム]
画家・作家。1936年、群馬県前橋市生まれ。1988年「バー螺旋のホステス笑子の周辺」で芥川賞候補、93年「犬」で川端康成文学賞、2007年『ブロンズの地中海』(集英社)で毎日出版芸術賞、11年『本の魔法』(白水社)で大佛次郎賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
hasegawa noboru
ろま〜な
ナッキャン