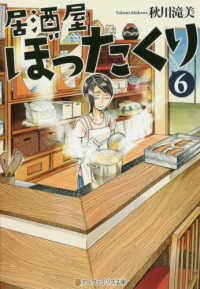出版社内容情報
「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。アクアリウムの誕生から現在までをたどるユニークな文化史。図版多数。
【著者紹介】
1964年生まれ。ベルリン自由大学、ベルリン経済大学を卒業。現在は客員研究員、フリーランスの文筆家、ノンフィション作品の編集者。邦訳に、『熊――人類との「共存」の歴史』、『月』(以上、白水社)がある。
内容説明
「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。その前史であるアクアリウムはいかにして誕生したのか。海中世界に憧れた人々の試行錯誤をたどりながら、現代の水族館が向かう先を見据えるユニークな文化史。
目次
最初の種―海洋の神秘
第二の種―小部屋、陳列棚、ケース
第三の種―魚をペットに
「情熱と勤勉」―開拓者たち
強くあくなき追求―ブームの火つけ役
海水アクアリウムから淡水アクアリウムへ―ガラスの中の湖
アメリカへの上陸―アクアリスト協会と博物館
異国の品種とその輸送―分かれる考え方
流行の見本市―居間用アクアリウムのさまざまな形式
「新種の劇場」―大型のアクアリウム
アクアリウムからオセアナリウムへ、そしてその先へ
水族館の暗い深層
著者等紹介
ブルンナー,ベアント[ブルンナー,ベアント] [Brunner,Bernd]
1964年生まれ。ベルリン自由大学、ベルリン経済大学を卒業。現在は客員研究員、フリーランスの文筆家、ノンフィクション作品の編集者
山川純子[ヤマカワスミコ]
名古屋に生まれ、鎌倉で育つ。慶応義塾大学文学部国史および美学美術史専攻、アリゾナ大学美術史(写真史)修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナーキー靴下
安南
夏帆
gecko
あかふく