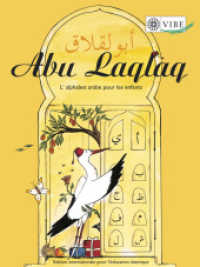内容説明
通勤電車、回転木馬、川沿いの工場地帯、きまじめで心配性の住人たち―1920年代、都会でも田舎でもないパリ郊外の現実を、いち早く的確に活写した詩的散文。ドアノーによるパリ郊外写真収録。
著者等紹介
ボーヴ,エマニュエル[ボーヴ,エマニュエル][Bove,Emmanuel]
1898年パリ生まれ。ユダヤ系フランス人作家。早くから作家志望で、多くの職を転々としながら書き上げた短編が認められ、1924年に『ぼくのともだち』でデビュー。続く『きみのいもうと』で作家の地位を固める。光と影の交錯する戦間期のフランス社会と、そこで蠢く人間模様を、特異な観察眼とユーモアで捉えた作品群は、多くの読者に迎えられる。晩年は体調を崩し、ナチスの脅威を逃れながら書きつづけ、1945年にパリで病没。戦後しばらくの間は忘れられていたが、1970年代後半から再評価が始まり、主要作品の翻訳も進み、今日では各国の読者から高く評価されている
昼間賢[ヒルマケン]
1971年生まれ。パリ第四大学博士課程留学。早稲田大学大学院博士課程単位取得退学。現在、早稲田大学非常勤講師。専門は、フランス両大戦間の文学・文化、ポピュラー音楽論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
28
ぼくのともだち(パリでもっとも不器用な男の独り言)やきみのいもうと(素寒貧な男の話)で駄目男を越える至高のクズ男文学をクリエイトした著者による、1927年に書かれたパリ郊外のとある町について書かれた短いエッセー。都会でもなければ田舎でもない街並みの景色やそこで暮らす人々をユーモアや皮肉交じりに書き出しながら、不思議と冷たさは感じない。どこにでもある町、だけどそこにいる人にとっては愛憎交じり合う特別な街。そんなおかしみを詩情として、散文として安堵感を与えてくれる。ロベール・ドアノーの写真も合っている。2017/12/28
長谷川透
26
あるかなしかの町。パリ中心から10㎞離れた所にあるこの町は、小さな自治体のごく一部を名指したものに過ぎず、何か名前をつけていなければ自覚的に存在さえも気にしないような町だ。しかしボーブがこの町のことを書いたのだから、彼にとって何かしらの思い入れがある土地なのだろう。ところがエッセイとも散文詩とも言い切れないこの小さな本からは、この町への特別な思いのような何かが全く伝わってこない。ボーブ文学の代名詞である「ダメ男」は出て来なくとも、彼のテクスト特有の妙な倦怠感が漂うが、微かに温かさもある。不思議な本だった。2013/11/17
凛
17
90年ほど前のパリ郊外、何の変哲もない或る町についてのエッセー、詩的散文。言ってしまえばただそれだけの本だ。なのにある種の本が持つ読んでいる間スッと周囲の空気が消えてしまう、意識を吸い取られる感覚がこれにはある。変に具体的な部分があったり普通すぎるのに詩的に切り取られているせいだろうか。「花屋では、とりわけ12時15分前に花束が売れるが、それは昼食に招かれた人たちが列車に乗る時間だからだ。」自分の住んでる町を彼に書いて欲しいと思った。見る人が見ればどんな町も素敵タウンになり得るのかもしれない。2015/09/25
きゅー
12
何事も起きない普通の町の日常的な観察記のようなものがボーヴの手にかかると詩的な随筆に思えてくるのが不思議だ。町の特徴を描き出すと言うよりは、そこに欠けているものが書き連ねており、もし凡庸な書き手であれば田舎町への蔑みのようになってしまうかもしれないが、本作からは、町への愛情を感じられる。父親が思春期の息子に寄せる感情のように、あけっぴろげではない愛情。本作で描かれているのは1920年代のものだけど、いまだこの町は健在という。訳者によれば、東京近郊に例えるなら京王線沿線の町のように感じられるという。2020/06/25
けんとまん1007
11
ポーヴ。初読み。自分にとっては、不思議な空気が漂う作家だ。アンニュイと温もり(人肌、息づかい)。どこにでもあるような田舎の街を切り取ったようなイメージ。でも、明らかに感ずるのは、日本ではないなということ。作家が日本人でないということ以上に、そう思わせる世界がある。もしかすると、自分の住んでいるところもこんな風に切り取れるのかもしれない。2014/04/12