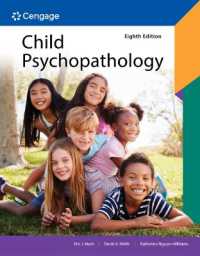出版社内容情報
スタリングラード攻防からベルリン攻略まで、「戦場の非情な真実」を記す。20世紀ロシア文学の最高峰グロースマンが見聞した戦場の実態。
内容説明
「20世紀ロシア文学の最高峰」ヴァシーリイ・グロースマン。スタリングラート攻防戦からクールスク会戦、トレブリーンカ絶滅収容所、ベルリン攻略戦まで、作家が最前線で見聞した“戦争の非情な真実”を記す。
目次
第1部 ドイツ軍侵攻の衝撃―一九四一年(砲火の洗礼(八月)
悲惨な退却(八~九月)
ブリャーンスク方面軍で(九月)
第五〇軍とともに(九月)
ふたたびウクライナへ(九月)
オリョール失陥(十月)
モスクワ前面へ撤退(十月))
第2部 スタリングラートの年―一九四二年(南西方面軍で(一月)
南方での航空戦(一月)
黒師団とともにドネーツ河岸で(一~二月)
ハーシン戦車旅団とともに(二月)
「戦争の非常な真実」(三~七月)
スタリングラートへの道(八月)
九月の戦闘
スタリングラート・アカデミー(秋)
十月の戦闘
形勢逆転(十一月))
第3部 失地回復―一九四三年(攻防戦の後(一月)
祖国の領土を奪回(早春)
クールスク会戦(七月))
第4部 ドニェープルからヴィースワへ―一九四四年(修羅の巷ベルジーチェフ(一月)
ウクライナ横断オデッサへ(三~四月)
バグラチオーン作戦(六~七月)
トレブリーンカ(七月))
第5部 ナチの廃墟のさなかで―一九四五年(ワルシャワとウッチ(一月)
ファシスト野獣の巣窟へ(一月)
ベルリン攻略戦(四~五月)
著者等紹介
ビーヴァー,アントニー[ビーヴァー,アントニー][Beevor,Antony]
1946年、ロンドンに生まれる。陸軍士官学校に学び、英陸軍将校として5年間、軍務に就く。除隊後は執筆活動に入り、“The Spanish Civil War”“Crete:The Battle and the Resistance”“Paris After the Liberation 1944‐1945”などを発表して高い評価を受ける。『スターリングラード運命の攻囲戦1942‐1945』(朝日新聞社)でサミュエル・ジョンソン賞など多数受賞する
川上洸[カワカミタケシ]
1926年京城(ソウル)生まれ。旧制東京大学文学部言語学科卒。スラヴ語専攻。旧ソ連大使館広報部、APN通信社東京支局に勤務ののちロシア語、ポーランド語、英語からの翻訳に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
ジュン
sasha
富士さん
そのあとに続く
-

- 洋書
- Nature Girl
-
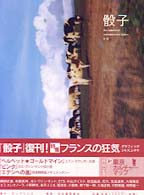
- 和書
- DICE 〈#25〉