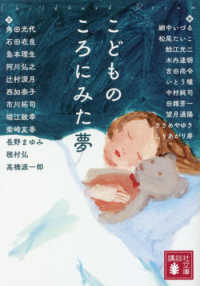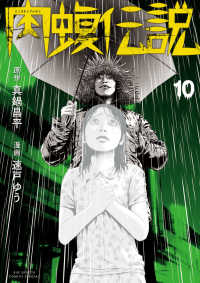出版社内容情報
大戦前後から昭和50年まで、炭焼・造林労働者として紀の国を転々とした著者が、その棲み跡を再訪した木の国紀行。行間から昭和林業の盛衰、世相の推移、野生動物や自然との交歓があぶり絵のように浮かび上がる。
内容説明
本書は、かつて私が棲んで働いたことのある山の現場を、あらためて再訪問した記録である。全部を網羅したわけではないが、とくに時代の節目となったようなところを歩いた。
目次
1章 われは炭焼きの子―大戦前後(わが出生の地―尾鷲;石の炭、木の炭―志古;炭焼きたちの戦争―四滝;消えゆく焼き子―シブケ;戦後の黄金時代―フカサコ)
2章 拡大造林の山で―昭和30年(炭窯と小屋をつくる―ナメ滝;青年作業班の結成―平井郷;義務教育免除地―道湯川;夏の下草刈り―ウズラ谷;高度経済成長のころ―西ン谷)
4章 最後の窯出し―昭和40年(安保闘争のあと―タケヤ谷;共同山のてんまつ―渡谷;炭焼学問―荒谷;父の最期―隧道口)
4章 あしたの森林―昭和50年(植えた、飲んだ、読んだ―ナメラ谷;中国生まれの広葉杉―滝谷口;拡大造林の終わり―大石谷;若木たちの冬―キリクチ谷)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kan Bin
1
昭和の林業を切り抜いた人が、リタイアに現地を登山で訪ね歩き現場のことを回顧する。 林業って、ただ木をきって運ばれて日本の家になっていくだけじゃない。昭和にがんがん伐採しまくって一世を風靡し、その後衰退していっただけじゃない。キツイ・キタナイ・キケンの3Kだけじゃない・・・ だけじゃないのよ、そうなのよ。山よ、木よ、里へ降りずに自然と木に向き合う数ヶ月の中の、自分との対峙、仲間との日常よ。 ロマンとノスタルジー溢れに溢れてやわらかい光になっちゃった、みたいな印象。図書館でめっちゃ地味に置かれてたけどね。2021/01/01
-

- 和書
- 蘭 らんファースト写真集