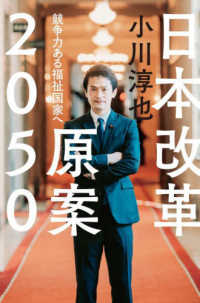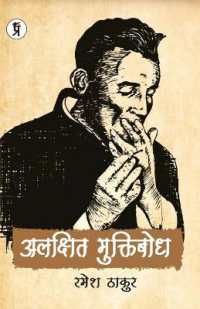出版社内容情報
山里での釣りや旅で出会った状況との対話から哲学と人間の現在を明示する。自然や労働の持つ意味も鮮烈に蘇える。本来哲学は、人間の生きている場のなかで真価を発揮するからである。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
21
16節_自然「日本には(自然環境という意味での)自然という言葉がなかった。…杉、猿、虫というように個別に呼びあってきたのであり、そのひとつが人、であった。そうでなければ…山の神や水の神を尊ぶ風習は生まれなかったであろう」 ◉(p.77)人間たちは少しずつ自然を加工する範囲を拡げていった。森を切り開き、大地を農地に変え、鉄鉱石を鉄に変え、川から水を引きながら、それまで人間の手の届かなかった自然を、人間の生活圏のなかに取り込んでいったのである。→その交流のことを労働と位置づける(加工と性質の発見、精神的交流)2023/06/18
アナクマ
20
「日々の疲れと、日々の楽しみと、日々の怠惰の中に身を置」く現代と、往復する田舎暮らしから哲学を生成する若き日の試論。80年代前半。文庫化希望。◉冒頭はヤドカリ放生会、カブトムシの修理業。14節_土「人の営みはすべて自然を加工することによって成り立っている」◉感想は本一冊分になりそうだから、ゆっくりと反応しよう。例えば19節_落伍者。過疎化した故郷に帰りたい子世代と〈帰らせたくない〉親世代のやりとりを、著者は観察・収集し、そして考える。ここでは、状況のタイムラグが生む悲喜劇のあることをメモしておきたい。2023/06/17
伊藤
3
誰がなんと言おうと名著。2009/10/18
ヤスミン
2
人間は労働に別の意味を付与することによって、労働を自分のものにしてきた。しかしながら、<企業のための労働>に移り変わっていく中で人々は営利目的以外に、労働と自己をリンクすることが困難であることを知る。労働は単なる<稼ぐための労働>となり下がってしまったのだ。古き良き共同体があった頃のエッセーが時代による労働の変遷を感じさせる。解決策が提出されていないのが悔やまれるところではあるが、色々と収穫のある本であった。2012/01/08
yanoms
2
本当に名著。この気持ちを忘れないようにしよう。もっと多くの人に読まれるべき。ちくま学芸か岩波現代はこの本を再販しなければならない。2011/11/24
-

- 電子書籍
- 月刊テニスマガジン 2020年12月号