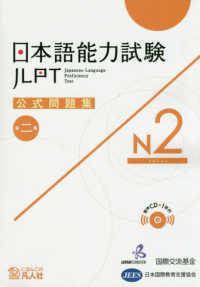内容説明
日本人の伝統的な自然観に迫りつつ、今日頻発する水害の実態と今後の治水のあり方について論じ、ローカルな自然に根ざした自然観の再生と川との共生を展望する。大熊河川工学集大成の書。
目次
1 川と自然を私はどう見てきたのか(日本人の伝統的自然観・災害観とは;近代化のなかで失われた伝統的自然観;小出博の災害観と技術の三段階)
2 水害の現在と治水のあり方(近年の水害と現代治水の到達点;究極の治水体系は400年前にある―堤防の越流のさせ方で被害は変わる;今後の治水のあり方―越流しても破堤しにくい堤防に)
3 新潟から考える川と自然の未来(民衆の自然観の復活に向けて―自然への感性と知性をみがく;自然と共生する都市の復活について―新潟市の「ラムサール条約湿地都市認証」への期待)
著者等紹介
大熊孝[オオクマタカシ]
新潟大学名誉教授・水の駅ビュー福島潟名誉館長・NPO法人新潟水辺の会顧問・日本自然保護協会参与・(公財)こしじ水と緑の会理事。1942年台北生まれ、高松・千葉育ち、1974年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)、新潟大学工学部助手、講師、助教授、教授、附属図書館長を経て、2008年新潟大学名誉教授、同年新潟日報文化賞受賞。専門は河川工学・土木史、自然と人の関係、川と人の関係を地域住民の立場を尊重しながら研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山口透析鉄
31
市の図書館本で。毎日出版文化賞を獲得したというのも納得の本でした。 日本の伝統的な自然観と、明治政府による中央集権的な手法(田中正造が象徴的に出てきます)との対比(民衆と国家の自然観の違い)や著者の半生が語られ、ベースにある事項が分かります。 21世紀に入ってからの実際の水害の豊富な実例を元に、治水事業がどのような隘路に陥っているのか、実際の住民運動等にも関わった経験をふまえて分かりやすく書かれています。 脱ダム宣言をした田中康夫長野県知事は私も正しかったと思いますよ。抵抗勢力、日本をダメにしています。↓2024/05/16
まると
23
毎年豪雨災害が起きるたびに、本当に地球温暖化だけが原因なのだろうかと感じていた。そうした疑問に真正面から答えてくれる素晴らしい本でした。著者によると、今起きている災害の多くは、被害が起きやすいところに無防備に立地してきたことが原因らしい。そして、水を一滴も漏らすまいとする国の治水対策には限界があり、被害をできるだけ低減する発想への転換が必要だと訴える。近代以前と同じような川との共生はもはや難しいが、その発想に学ぶものは多いと感じた。毅然とした態度で国の誤りを指摘する、学者の矜持も感じさせてくれる一冊です。2021/07/12
gotomegu
12
立川オリオン書店で出会った。生活レベルで感じる自然観と国を治める自然観とではかなりちがう。今は都市化が進んで国目線の自然観に近くて、川と生活がコンクリートできっちりと仕切られてしまっている。川の水が増えたら一滴も漏らさずに海まで流すことを目的とされている。かつては、川はもっと身近なものであり、正面から戦うのではなくうまく受け流していた。影響の少ない場所へあえて氾濫させることでやりすごしていた。ダムは土砂が溜まってしまうので100年ともたない。山林についてはあまり触れていなかったのが残念。2021/02/17
おにぎりまる
4
初めての大熊先生の著書。「民衆の自然観」が破壊され、「国家の自然観」を取り込んでいったことによる弊害について、分かりやすく書かれていた。私のもやもやを言語化してくれたようですっきり。著者が言うように、国家の自然観に対抗する、その地域の自然観をつくっていけたら、どんなに素晴らしい社会になるだろうか。2023/03/24
Hiroki Nishizumi
4
参考になった。土木治水専門家としての集大成本となっているが、冒頭に山川草木悉皆成仏、石にも心を読み取る、など伝統的自然観が書かれている。本の大部分は水害や治水体系の具体例だが、最後に宇沢弘文の社会的共通資本へ言及してあるところで初めて納得した。実はそういう方とは知らなかった。2021/02/24