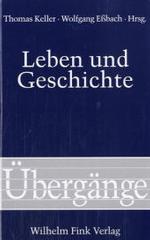出版社内容情報
昭和最後の9年間、わずかに残る伝統マタギの集落に通い、狩り、皮はぎの神事、熊祭り、山の神祭り、小屋がけ、火起こし、装束や猟具など撮影した記録。347枚の写真と聞き書きから伝統マタギの全貌が浮かび上がる。
目次
伝統的なマタギの世界―大正・昭和初期の姿(装束;履物 ほか)
玉川マタギ―集団的クマ猟と生活技術(春マタギ;門脇シカリのマタギ語り(『隆吉の七十年』より) ほか)
百宅マタギ―山の神信仰と熊祭り(冬の百宅;春の訪れ ほか)
里マタギ―伝統的ウサギ猟(巻狩り;ヒクグシ猟)
鷹匠―クマタカによるウサギ猟(鷹狩り;トヤ(鷹小屋))
著者等紹介
千葉克介[チバカツスケ]
1946年、秋田県角館町生まれ。写真家。1970年から東北を中心に活動。1979年、太田雄治著『消えゆく山人の記録 マタギ』で民具その他資料の撮影を担当。マタギに興味を持ち、その後も撮影を続ける。1988年「黎明舎」設立。世界環境写真家協会会員。2000年、全国観光ポスター展で銀賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
96
昭和時代のマタギの生活を、写真と共に紹介している。本に出てくるいくつかに場所は、ダムの底にあるという。そんな所は他にもあるだろう。山や川から食べ物をいただく、獲物が獲れて解体する時も祈りを捧げる。山を敬愛していることがよくわかる。山の神は女性であり醜いため、魚のオニオコゼの干したものを山の神に捧げる習慣も知った。山を開発のため多くの木を伐採したり、トンネルを作ったり、宅地にしたりマタギという人たちは嘆いているのではないか。彼らがいなくなるのは時間の問題かもしれない。図書館本 2024/12/17
たまきら
33
素晴らしい記録です。山と共に暮らす人々がなぜ消えたのか。そこにはもちろんいろいろな要因があるのでしょうが、このような形で「山を知る人」を失うということはクマにとっても損失な気がしました。真の共生とはどういうものなのだろう。・・・そんなことを考えつつも、様々な儀式や昔の装束の写真に夢中になりました。むかし山形でいただいたクマ汁、おいしかったな~。2019/11/28
鯖
19
今はもういないマタギと呼ばれた熊狩りの専門集団。昭和の終わりに、秋田の各地方のクマの狩り方、とどめの差し方、捌き方、肝の取り出し、火おこしの方法とありとあらゆるマタギの狩りの写真が載った本。捌くのは集落まで引きずってきてからとか、秘密の言葉で引導渡すとか、アイヌの熊狩りの風習に似たものも多いんだなあと思った。こないだミッドサマー見ちゃって、クマーってなってるところだったんですけども、やっぱりクマって特別な存在の獣なんだなあと改めて思った。2021/10/10
剛腕伝説
11
消え行く秋田のマタギの文化。先人の知恵が詰まったその技は細々と現代に生きている。 山で火を起こせないマタギはいない。火さえ起こせれば、最低限の食料で山で生きていける。 熊の解体写真を見ていると、複雑な気持ちになる。目を見開いた顔、皮を剥がれた死骸、 マタギも職業として熊を猟る、熊も生きるために必死で抗う。ビーガンではないけれど、ビーガンの人達の意見も分かるなぁ。とか言いながら、肉を食べる私。2024/10/22
yoneyama
8
昭和末期S57〜H2の、秋田のマタギ写真記録集。ライブな写真あり、解説的写真あり、面々のいい顔の写真もあり。色々な経緯で刊行されず、2019発行。クマの食べ方、胆の取り方、火の起こし方、野営の仕方、雪の上の座り方、神の祀り方、登山愛好家として、知りたいことがたくさん。 法隆寺宮大工や竹内洋岳への聞き書きインタビュー本が面白かった塩野米松氏の巻末あとがきで、この写真家の人となりが知れて良い。 2021/05/16
-

- 電子書籍
- ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロ…