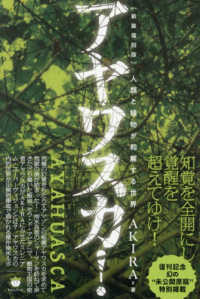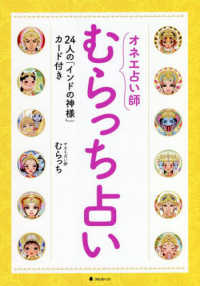内容説明
刺身、すし、てんぷら、出汁、雑煮、おせちなど、世界が注目する「日本料理」形成の謎に迫る。縄文から現代まで、料理から調理法・調味料・食器具・食習慣まで、壮大なスケールでたどる「和食文化史」。
目次
第1部 日本食文化の基層と源流―モンスーンアジアに位置する日本列島(日本の風土と基層としての発生期の日本食;お米はこうして日本の常食(主食)になった―日本型食生活の夜明け
源流としての中国に学んだもの)
第2部 日本料理の成立と展開―受容と改創のシンフォニー(万葉歌が語る奈良時代の食;中国伝来の調菜文化が起こした第二次日本食文化大革命;うまみの文化を決定づけた出汁の文化;京都料理とは何か―日本料理の重鎮として;江戸庶民の食事情;漁場から始まる日本の刺身文化;改創の極みとしてのすし文化;てんぷら(天麩羅)の謎を解く)
第3部 年中行事で花開く日本料理―正月を中心に(雑煮を祝う;おせちと七草粥)
著者等紹介
奥村彪生[オクムラアヤオ]
日本で唯一の伝承料理研究家。飛鳥万葉時代から江戸、明治、大正ならびに昭和の戦後まで、全国のお雑煮や、まんが「サザエさん」などの様々な料理を文献記録に基づいて再現、展示会を開催。現在も御食国若狭おばま食文化館(福井県)で順次展示されている。世界の民族の伝統料理にも詳しい。2009年、めんの研究で学術博士(美作大学・大学院)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件