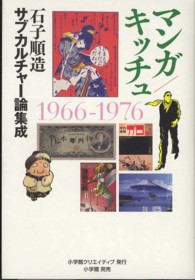著者等紹介
瀬戸山玄[セトヤマフカシ]
1953年鹿児島県市来町生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。WORKSHOP写真学校・荒木経惟教室に入塾後、1978年に入社の映像制作会社を経てフリー。2000年からドキュメンタリスト・記録家として文筆、写真、映像を駆使した活動を開始。技術の伝承と領域横断の新しい道を探る。岐阜現代陶芸美術館での展示映像制作をふくむロドチェンコ・プロジェクトは03年グッドデザイン賞審査委員長特別賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Kawai Hideki
82
今年の八十八夜は5/1。茶摘みの季節。日本のお茶の生産の約4割を占める緑茶王国静岡県。緑茶生産農家が多い中、わざわざアッサム系の茶の木の血統をひく品種を育て、国産紅茶のトップブランド「丸子紅茶」を作り上げた村松二六さんの想いに迫る。明治維新後に徳川家家臣から農民になった多田元吉の遺志と、彼がインドから伝えた紅茶の原木を継ぐ。栽培、萎凋、揉捻、乾燥の全工程に、それぞれ試行錯誤の苦労があり、絶妙なタイミングの見極めがある。「直接、茶葉を手で触る感触や温度、香りやらを感じて作る」それが「ほんとの茶師」なのだ。2016/05/08
あちこ
3
わたし用に借りた本。これだけの情熱を注いだ茶葉が、まずいはずがない。模索しながら進む姿勢を見習いたい。2015/02/12
遠い日
2
「農家になろう」シリーズ7。茶農家の村松二六さんの仕事。静岡の茶農家、それも、紅茶の茶葉を生産している村松さんのこだわりがすばらしい。緑茶ではなく、紅茶。それからさらにウーロン茶に挑戦。「紅茶は生きもの」だという村松さん。摘んだ葉の酵素を上手に働かせるために、繊細な職人技を極めてきた。「売れる商品ではなく、買ってくれる商品をつくる」のが目標と言い切る覚悟がかっこいい。2025/02/18
ochatomo
2
児童書ながらハイレベルな情報 未来を広げる意味かと思う 茶の集まりで10年前村松さん宅見学したが、ここまで詳しく知れなかった 写真の力が大 第3次牛肉オレンジ交渉が和紅茶再開のきっかけと気づく 2015刊2017/08/22
めいみー
1
一般的なお茶農家さんではなく、日本の紅茶(最近は烏龍茶なども)栽培・製造のアイコン的な人物を取り上げている。子供向けの本ながら専門的なこともきちんと押さえてある。2015/12/13