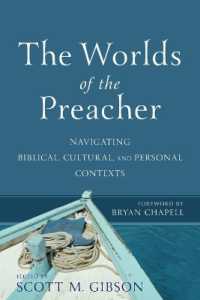内容説明
教室リフォームプロジェクト、お掃除プロ制度、Sケンあそび、作家の時間…。なにかを「やらせる」のではなく、「信頼」して「まかせる」と、子どもたちはおどろくほどの力を発揮し、自分たちでクラスをつくり、学びあい、成長する。ごくふつうの公立小学校に勤務する著者が、自らの実践をもとに、クラスを「最高のチーム」へと変身させる方法を伝授。教室で使えるチームゲームの付録つき。仲間と協力する楽しさを、あそびながら体験できる。
目次
第1章 サイコーのクラスのつくり方(劇的ビフォーアフター 教室リフォームプロジェクト;自分で工夫できれば楽しくなる!お掃除プロ制度 ほか)
第2章 子どもが主役の授業づくり(作文の読者って、誰なんだろう?;国語の授業が読書離れを引き起こす? ほか)
第3章 がんばらなくてもいい、仕事の仕方(ボクの一日実況中継 家にもち帰らない仕事の仕方;育児休業のススメ ほか)
第4章 子どもが変わる一番の方法は、ボクが変わること(ボクがオモシロ先生をやめたわけ;先生がファシリテーターになるためのかかわりスキル一〇ヵ条 ほか)
著者等紹介
岩瀬直樹[イワセナオキ]
埼玉県狭山市立堀兼小学校教諭。ファシリテーター。学びの寺子屋「楽学」主宰。EFC(Educational Future Center)理事。西脇KAI所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
き
52
クラス作りの苦悩や考え方を、ざっくばらんに語りかけてくれるような本。自分たちの教室を「学びやすく生活しやすく美しく」リフォームしていくことや、子どもが主体となる実践例、文学サークルなどが興味深かった。この著者の別の本も読んでみたいと思った。2021/07/24
草食系教師
4
率直な感想としては、頭では理解できるが、実践していくには根気と教師としての力が必要だと感じた。あと、その学年の子どもたちの特性にも合わせてどのように実践していくかだと思った。夫婦共働きの生活については、私自身耳が痛い。家のこと、子育ては共にやっていくもの、そのためには働き方を変えなければ…というところは印象に残りました。温める言葉を増やす実践(ポケットとクリップ)は、私も苦手なのでやってみようと思った。色々と書きましたが、これからも大切にしていきたい一冊です。2012/04/02
Arick
3
再読。今回気づいたのはp.147「クラスのベースを「子どもたちへの信頼」におきました。」ここを読んでびっくり。信頼ベースって、子どもたち同士の信頼関係と思っていましたが、まずは、僕たちの子どもたちへの信頼なんだと。簡単に書いているけれど、これを真に意識するって結構大変。でも目指したい。2016/08/24
草食系教師
3
初めて読んでから3年たったんだな。(こういうことがわかるのも読書メーターのよさやな)当時の率直な感想「理解できるが無理だろう」は、あの頃の自分が本当によく表わされてる。あれから3年たって、色々な本も読んで、いろんな経験もして、見える実践だけじゃなくてその根っこにある理論的な部分、一般化できる部分まで「つながる」ようになってきた。最近、よく読む菊池省三先生と形は違えぞ、根っこの共通点は同じだということが分かるようになった。この同じ根っこから、自分なりの実践をしたい。2015/06/06
もでぃ
2
4:1の法則を意識しよう。2017/06/18