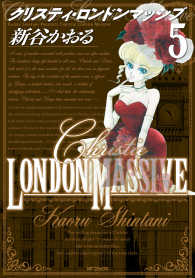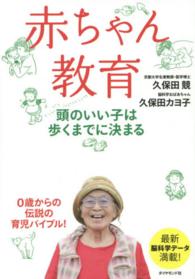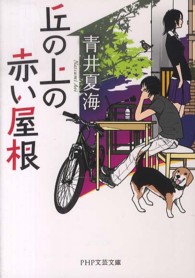内容説明
近代的な市民社会へのゆきづまり感が強まるなかで、前近代の象徴ではなく、未来への可能性として「共同体」が語られるようになってきた。群馬県上野村と東京との間を行き来して暮らす著者が、村の精神に寄り添うことをとおして、自然と人間との基層から新たな共同体論を構想する。
目次
第1部 共同体の基礎理論(現代社会と共同体;日本の伝統的な共同体を読み解く;共同体のかたち;日本の自然信仰と共同体;都市型共同体の記憶;共同体と近代国家;共同体の基礎理論に向けて;社会デザインの思想―「個の知性によるデザイン」から「関係によるデザイン」へ)
第2部 新しい共同体をめぐる対話(自ずからなる知恵―「食の自治」から「暮らしの自治」へ;お金は等身大の世界にかえれるか)
著者等紹介
内山節[ウチヤマタカシ]
1950年、東京生まれ。哲学者。1970年代から東京と群馬県上野村を往復して暮らす。NPO法人・森づくりフォーラム代表理事。『かがり火』編集長。東北農家の会、九州農家の会などで講師を務める。立教大学大学院教授、東京大学講師などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
26
共同体とは何かを農村の営みから考察する。一言で言えば、とても良かった。平易な言葉で、ムラ社会の存在意義を説いていた。一冊買おうと思う。2016/12/01
ドン•マルロー
14
いわゆる「西洋的」な共同体の本ではない。筆者が農村部で暮らしているというのもあるだろう。おもに自然との融和や土着信仰といった、日本独自の共同体にフォーカスした共同体論である。観念的ではなく、読んだあとに手からぱらぱらとかわいた泥の断片が落ちてきそうな、そんな類の本である。2019/03/06
アナクマ
4
(p.37)お金が必要になった人だけが,ロープを使ったりして大量採取できるのである。大量採取するときは,集落の人たちが採らなければならない理由を承知している,納得していることが必要である。つまりシノブとイワタケは集落の共有財産なのである。誰の山のものでもそれは変わらない。普段は手の届く範囲のものだけを採って「資源の保全」をはかり,誰もが納得するような理由でお金が必要になった人だけが「保全された資源」を採取する。2016/11/28
shokosmo
4
思想・精神から共同体を捉えなおす。日本古来の自然との関わり、他者との関わりを考えることができる。その上で、近代化とはなんだったのか?についての示唆を得ることができる。近代化と近代化以降を論じるものが多いなかで、それ以前の精神を考えることができるのは貴重な機会かと。2014/03/27
井上岳一
3
共同性は必要だが、共同体の負の側面(閉鎖性や因習)をどう乗り越えるか。そのことにいつも悩んできた。でも、本書を読んで、共同体の負の側面が、かなりの部分、近代以後に形成されたものだということを知った。天皇制とひも付けられたイエ制度、神仏分離と国家神道への統合、そして、ムラの自治の剥奪と国民国家化。これらが共同体の矛盾を生み出したのだと思う。近世以前の自治的共同体ならば、或いは、負の側面は乗り越えられるかもしれない。過去を丁寧に見返すことで、未来が見えてくる好著。近年の内山節の著書の中では出色。2015/06/05