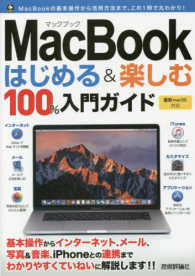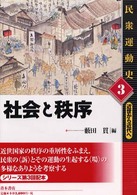目次
朝ごはんはしっかり食べます
順番に食べるのがロシア式です
おやつの後は、少し軽めの晩ごはんです
暖炉で煮るスープ料理が発達しました
パン生地料理が豊富です
台所の様子を覗いてみると
一週間の料理です
別荘での野菜づくりが夏の楽しみです
保存食づくりで大忙しです
お客さんは大歓迎します
マナーを守って気持ちよく食事します
季節の料理があります
地域によって料理が違います
ロシアのごはんをつくってみましょう
もう少しロシアのごはんの話
著者等紹介
銀城康子[ギンジョウヤスコ]
1956年、青森県生まれ。管理栄養士。2年半フランスに滞在し、フランス在住日本人の食生活調査、フランス各地の日常食調査を行なう。帰国後も、非常勤講師や執筆活動をしながら、世界各地の日常食調査を続けている
山本正子[ヤマモトマサコ]
1964年、千葉県生まれ。イラストレーター。東京デザイナー学院商業デザイン科卒業。児童書や教材、雑誌などのイラストを手掛ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
321
ボルシチ、ピロシキ、ペリメニくらいしか思いつかないロシア料理(なんとも貧困なイメージ)。ある日の朝ごはんは、白パン、カーシャ、スープにゆで卵、紅茶となかなかの充実ぶり。休日は昼ごはん、平日は晩ごはんがメインのよう。食材ではビーツの多用が目立つ。お料理として特徴的なのは黒パンと(伝統的にはペチカを使った)スープ料理の数々(おなじみのボルシチやウハー、サリャンカなど)。どれも美味しそうだし、冬の夕べに暖かい室内で食べるとほっこりと幸せな気分に浸れそうだ。2023/08/08
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
66
出た!父の国ロシア。肉料理が主流だが魚料理も豊富。ピロシキを揚げるのは日本からの逆輸入。油は貴重なので揚げないピロシキ!沢山食べれるし中身何入れてもいい!多分!コーヒーよりも紅茶を沢山飲む。ロシアンティーはジャムを紅茶に入れると思われているがジャムを舐め舐めしつつ飲むのがロシア式。気が付くと一瓶空っぽですwロシア人は虫歯も多いです!私がよく野菜干したり漬物が。が。ロシアも保存食を非常に沢山作るからで長い冬を過ごす正にライフライン。いつ、帰れるのか分からないけどね😢😢😢2023/07/25
seacalf
54
読友さんの感想から気になった絵本シリーズ。ロシアというと現在はウクライナ情勢の影響できな臭いイメージがつきまとうが、食べ物の話になると俄然親しみを覚えるから不思議なもの。ロシアの人でも黒パンばかりでなく朝は白パンを食べるのね。餃子とペリメニの違いに納得。食べたくなる。意味合いは違うが、「いただきます」「ごちそうさま」のように食前・食後の挨拶のロシア版がきちんとあるのも面白い。この絵本シリーズは管理栄養士さん視点の解説があり、けっこうがっつりした内容。少しずつ他の国の絵本も読んでみたい。2023/09/06
FOTD
23
暑い日が続くので先日「タイのごはん」を読んだが、その流れで逆に寒い国の食事はどうなのかと思い手に取った本。朝ごはんをしっかり作り、前夜に準備しておくこともある。これはタイとは全く違う。昼ごはんが最も重要。だが、現在では簡略化されている。晩御飯は軽め。ペチカを使った、スープ料理、パン生地料理、が発達した。なるほど納得した。長い冬のために保存食作りもあるし、季節の料理もある。この本はレシピ本ではなく、食事の背景にある文化や自然環境についても書かれているので、大枠を知るには適した本であると言えよう。2023/07/29
たまきら
20
すっかりシリーズにはまりまして…好きな国からのんびり攻めております。いや~おいしそうなうえに、その国の文化がきちんと紹介されていていいですよ!またオタマさんが「ロシア行きたいな~」…2016/08/03
-
- 洋書
- Human Blues