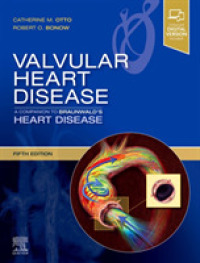- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
出版社内容情報
フォーで明けるベトナム、塩乾物好きのカンボジア、モチ米のラオス、油と豆のミャンマーを探訪。
内容説明
フォーで始まる朝のベトナム、干物と塩辛のカンボジア、モチ米のラオス、油と豆のミャンマーなど、米と魚醤の地・東南アジアの食を探訪する。
目次
はじめに 一杯のフォーから見えるもの
第1章 ベトナム人は何を食べているか
第2章 ベトナムの香り、ベトナムの味
第3章 カンボジアの食文化
第4章 ラオスの食文化
第5章 ミャンマーの食文化
第6章 東南アジアの食文化の特色
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NoDurians
3
研究的な調査ではないのでその信頼性のあたりが弱いと思うけれど、それでもこのような形で食文化をまとめた本はないので、とても大切だと思う。米文化の広がりは興味があるところです。司馬遼太郎がどこかで米は多くの人口を支えられるみたいなことを書いていて、それ以来。似ているところもあり、違うところもあり、と文化の多様性とそれぞれの大切さが実感できます。2012/09/15
Witch丁稚
1
20世紀最後の方のベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの食の記録。歴史的に文化圏が今の国境と異なっていたり、複数の民族がいたりする。それでも特徴的なのは米、魚醤、塩辛、中国とインドの影響、外食特に朝食。面白かったのはラオスのナレスシの起源について、現在のラオ族の祖先ではなく扶南国などのモン•クメールまたはそれ以前の少数民族の可能性があり、誰がというよりもこの地にあった食の形態がこの地に踏襲されている可能性。確かに初代が持ち込んでも2世3世はその地の食べ物に馴染んでいくだろうなという実感はある。2024/06/22
-
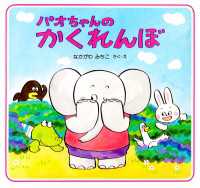
- 電子書籍
- パオちゃんのかくれんぼ