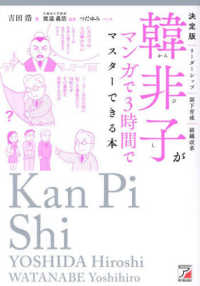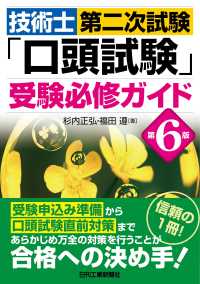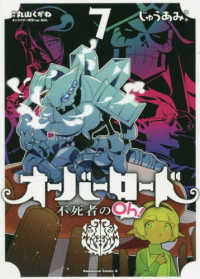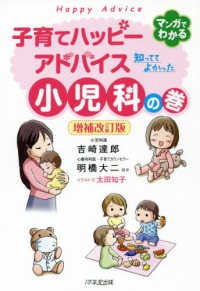出版社内容情報
スーツやブラジャーまで手作りした女たち。洋裁教室や暮しの手帖に戦後の衣服革命を読み取る。
内容説明
今では子どもから老人まで日本人のほとんどが洋服を着ている。しかし日本人の服装がほぼ完全に洋服に変わったのは昭和二〇年以降のことである。敗戦直後の困難な暮らしを生き抜くなかに、女性主導の静かな革命があった。洋裁教室ブームに象徴される衣服革命である。本書はこの歴史に埋もれがちな「洋裁の時代」を検証し、この時代に女性たちがどのようにして洋服を自分のものにしていったかを明らかにする。
目次
第1章 花開く洋裁学校(衣服革命と洋裁教育;洋裁学校と個性豊かな創設者たち ほか)
第2章 女の自立を支えた洋裁(高収入だった洋裁内職;洋裁が家計を支えた実態 ほか)
第3章 農村の洋服化(野良着の魅力;農村の洋服化へのみちのり ほか)
第4章 腰巻からズロースへ―洋装下着の普及史(和洋折衷下着から始まった洋装下着;戦後の下着―洋装下着の普及 ほか)
特論(桑沢洋子の仕事着;『暮しの手帖』の直線裁ち ほか)
著者等紹介
小泉和子[コイズミカズコ]
1933年、東京生まれ。京都女子大教授、生活史研究所主宰、昭和のくらし博物館館長。工学博士。日本家具・室内意匠・生活道具史専門
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Aby
7
和装から洋装へ,どのようなプロセスで女性の服装は移行したのか.◆そういえば,明治生まれの祖母は生涯和装だった.昭和10年代生まれの母は高校卒業後「洋裁学校」に通っていた.◆メモ:第3章 農村の洋服化 大正末~昭和4……洋装が実生活とまだ大きく離れていた時代,昭和5~昭和20……大恐慌から戦争へ,昭和20年代……婦人解放と生活改善の模索のなかで,昭和30年代前半……実用的な洋装への精力的研究と実践,昭和30年代後半~40初め……農村経済の都市化と農作業着の既製服化2023/03/02
しまめじ
3
洋裁はどのように日本の家庭に入ってきて広まってそして今のようにほぼ100%洋服を着るようになったのか、についての詳細な調査研究の本。戦前からの婦人雑誌の洋裁記事を丹念に探したり、聞き取りで当時の様子を確認したりで、戦後急速に洋服が広まった理由と原因を探ります。戦争未亡人への斡旋仕事や家庭内内職から洋裁をする人が増え、その人たちから一気に洋裁が広まっていったのですね~。祖母が和裁をやっていて、自分の服をほとんど自作していたのと、子供の頃親戚に服を作ってもらったことなど思い出しましたね~。2014/06/20
takao
2
ふむ2023/05/11
さんとのれ
2
偶然と必然が重なったとはいえ、まれにみる驚異的な速さで着物から洋服へと移行した日本の服装事情。女性の地位向上のため、家族を支えるため、限られた情報と道具で洋裁をものにしていく様子は、すさまじくもあり頼もしくもある。歴史だけでなく、文化、ドレメその他の原型の比較やコンセプトの違いなど、技術的な話もあり。2014/10/22