内容説明
「参加するまちづくり」とは、まちのビジョンをそこで暮らす住民が共有し、地域のことは地域で決めるという自由で開かれたまちづくりである。「情報共有」「体験共有」「意見表出」「創造表現」「意見集約」「変化の記録」という6つのコミュニケーション術を通して地域の意志をつくり出していくまちづくりワークショップの知恵と技を伝授する。
目次
第1章 「まちづくりワークショップ」って何だろう?
第2章 プログラムに託されたコミュニケーションの知恵と技(まずは共通の土俵を作る―情報共有コミュニケーション;「百聞は一見にしかず」の精神で―体験共有コミュニケーション;考えられることはすべて出してみる―意見表出コミュニケーション;創造し表現する楽しさを味わう―創造表現コミュニケーション;全体と個の関係づけを工夫する―意見集約コミュニケーション;場の変化をとらえて記録する―その他のコミュニケーション)
第3章 「丸池復活プランづくりワークショップ」を読み解く
第4章 「まちづくりワークショップ」Q&A
著者等紹介
伊藤雅春[イトウマサハル]
1956年、愛知県名古屋市生まれ。大久手計画工房代表。NPO法人玉川まちづくりハウス運営委員。まちづくりワークショップ歴13年
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
5
装丁は絵本のような厚めの紙を使って親しみやすいデザインだが、中身はふつうの文章がある。創造性なくしてまちづくりは進まない。昨日の市民の集いでは、創造研究者からのご説明では、過去、現在、未来の時系列を意識して、累積的なイメージのまちの厚みの価値を改めて知った。そうした厚みのあるまちづくりの営為だが、なぜか、失敗するケースもある。まねようとしてもそんな単純なことではないからだ。魅力的なまちには人が楽しんでいるためにそこに耳目が集まるのである。自分の地域を誇りに思えないために誤解を生む。楽しいまちに楽しい人か。2013/04/11
阿部
0
易しい一冊。現場を経験し、一歩戻って考える手引きとしては良いと思う。 演劇事例もいくつか掲載されている。2018/04/18
-
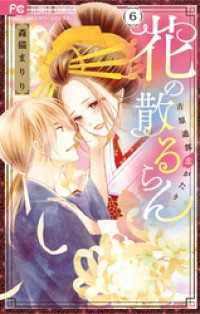
- 電子書籍
- 花の散るらんー吉原遊郭恋がたりー(6)…
-
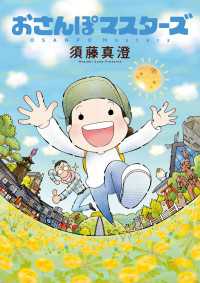
- 電子書籍
- おさんぽマスターズ ビームコミックス





