内容説明
イノベーションへの誤解が、ここまで日本をダメにした!「敗戦」を続けてきた日本の半導体、「売れるもの」を作れなくなった電機業界の実態とは。
目次
第1章 電機産業壊滅の真因(なぜソニーはイノベーションを起こせなくなったのか?;シャープは本当に「世界の亀山モデル」をつくっていたのか?;水道哲学が消失したパナソニック)
第2章 日本半導体敗戦、再び(4回も敗戦していた日本DRAM;自己決定能力が欠けていたルネサス)
第3章 激変する世界の半導体・電機産業(世界市場はどこまで成長するか?;ネジ・クギになった半導体;半導体はどこで製造されているか?;世界の工場となった中国の半導体産業;SNS時代の半導体;スマホ/タブレット時代の到来;終焉を迎えたウィンテル連合時代;アップルとサムスンの訴訟問題とクリステンセン氏の失言)
第4章 日本のものづくり再生への道筋(日本が同じ間違いを繰り返す原因;「組織のジレンマ」を回避せよ;LSIの3次元化を制する者が次世代を制する;日本は半導体メモリに回帰すべきだ;新メモリの登場え新市場創出が鍵に;全員マーケティングに参加せよ;地球的経営ができる経営者を!)
第5章 自動車産業に忍びよる不安(半導体技術者は部分最適しかできない;EV化の大津波がやってくるEVがクルマ全体の何%まで普及するか?;ロジャーズの16%普及理論;デファクト・スタンダードはもっと早く決まる;中国・山東省の低速EVの衝撃;EV化をビジネスチャンスに)
著者等紹介
湯之上隆[ユノガミタカシ]
1961年、静岡県生まれ。1987年、京都大学大学院(修士課程原子核工学専攻)卒業後、日立製作所に入社。以後16年半に渡り、中央研究所、半導体事業部、デバイス開発センター、エルピーダメモリ(出向)、半導体先端テクノロジーズ(出向)にて、半導体の微細加工技術開発に従事。2000年に京都大学より工学博士。2003~2008年に、同志社大学にて半導体産業の社会科学研究を推進。兼任で長岡技術科学大学客員教授。現在、微細加工研究所の所長としてコンサルタントや執筆活動に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mazda
mazda
とうゆ
MAT-TUN
富士さん




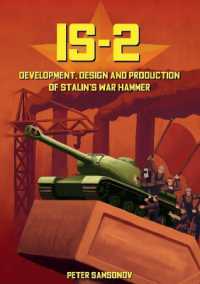
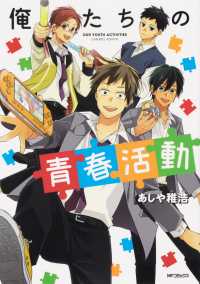
![あまんちゅ! 〈14〉 - 春色アクリルスマホスタンド付初回限定版 [特装版コミック] ブレイドコミックススペシャル (限定版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48000/4800008263.jpg)


