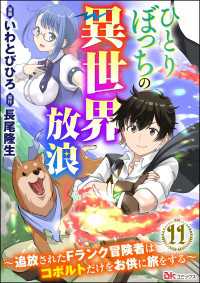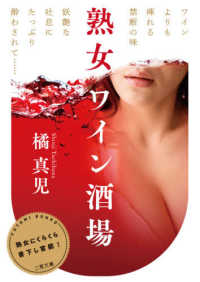出版社内容情報
2000年代以降、日本における数学を取り巻く環境は激変している。数学の必要性・重要性が産業界や省庁などで見直され、産学官の連携も出来上がりつつある。しかし一方で、STEAM教育などの取り組みはなかなか浸透しておらず、AI産業なども後手に回っているのが現状である。
本書では、数学が自然科学、工学など他分野や産業界にどのように関わって社会の問題解決に貢献しているか、また、新たなイノベーションを創出しているかを紹介する。
第1巻では、最適化理論、耐量子計算機暗号、数理ファイナンス、力学系、感染症の数理、ネットワークなど、産業界と協奏する研究を紹介し、それぞれの分野における数学の役割を紐解いていく。
また巻頭では、長年数学と産業界に軸足をおいて活躍されている研究者が考える、キャリアパスや人材育成についての提言を座談会として掲載した。
本書をきっかけに、数学・数理科学とその応用分野の発展に多くの方の深い関心が寄せられることを期待する。
内容説明
社会のさまざまな問題を解決するために、どのような数学が必要なのか。第1巻では数学と産業界で交差する研究を紹介する。
目次
座談会 産業と数学におけるキャリアパスと人材育成
序章 数学の展開に期待して―人類の知識財産の活用
第1章 社会、産業と最適化
第2章 量子情報処理
第3章 耐量子計算機暗号
第4章 数理ファイナンスと金融工学
第5章 力学系と安定性、制御、感染症の数理
第6章 不確実性:数学・数理科学の視点から
第7章 ネットワーク、グラフとSNS
第8章 数学のひろがり―行列式と因数分解の視点から
著者等紹介
岡本健太郎[オカモトケンタロウ]
1990年、山口県下関市生まれ。九州大学卒業。博士(数理学)。切り絵作家として国内外で積極的に活動。同時に大人向け数学教室「和から株式会社」において、数学や数学を使ったアートの講師も務める。JST/CRDS特任フェロー兼任
松江要[マツエカナメ]
広島県生まれ。九州大学マス・フォア・インダストリ研究所准教授,同大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所WPI准教授。JST/CRDS特任フェロー兼任。京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻博士後期課程修了。博士(理学)。東北大学、統計数理研究所(文部科学省委託事業『数学協働プログラム』)を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shin
icon