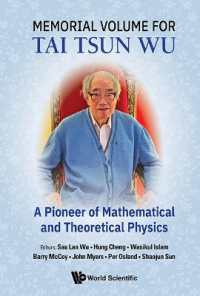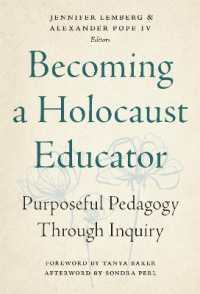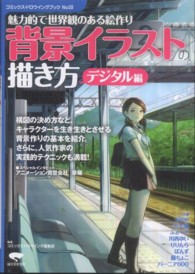目次
第1部 Kepler問題(「プリンキピア」の問題設定と論理構成;「順Newton問題」の解法と重力の導出;「逆Newton問題」の解法と『プリンキピア』の限界 ほか)
第2部 力学原理をめぐって(Eulerによる力学原理の整備;新しい問題―拘束運動とその解法;Daniel Bernoulliと非剛体的拘束運動 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
『プリンキピア』は引力の中での運動(ケプラー問題)に取り組むが、運動が与えられる物体に働く力は求められても(順ニュートン問題)、力が与えられた物体の運動は求められなかった(逆ニュートン問題)。本書は、ニュートンの力学がニュートン力学に転換する1世紀を辿り、幾何学によるニュートンの計算に代えて微積分学を導入するライプニッツ、ヴァリニョンの順問題の微積化、ヘルマンとヨハン・ベルヌーイの逆問題の微積化等を経てラグランジュの『解析力学』に至る。その背景にはフランス革命時代の科学者集団と産業の連携の形成が見られる。2019/02/27
ヨウジン
2
作者による入念な資料調査によって「ニュートンの力学」から「ニュートン力学」へどのように変化したかを知ることができます。とても重厚な内容ですので是非一読をお勧めします。2011/05/01
Akiro OUED
1
ニュートンは、ケプラーの法則を幾何学で説明した。偉業だけど、力学の基本方程式を力を使わずに表現したラグランジュも偉い。量子力学創世記には食傷したけど、古典力学の形成物語は新鮮だ。概念の記号化は、力だ。政治の世界では言葉の陳腐化が著しいので、ライプニッツに記号の力を学ぶべきだね。2025/04/14
-

- 和書
- 先視の王女の謀 角川文庫