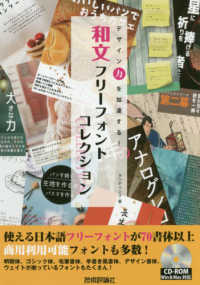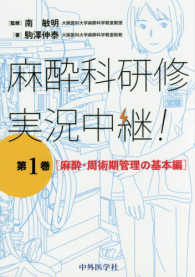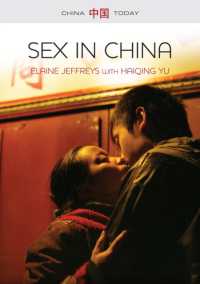出版社内容情報
戦後日本は高度経済成長を経て先進国の仲間入りを果たし、今日では世界で最も高齢化の進んだ国として持続可能な〝福祉国家〟構築のフロントランナーとなっている。しかし、目に見える症状に応急処置を施すだけの政策が多く、問題の根本的な解決には至らない。
困難極まる2030年代を迎えないためには、2020年代に「十分な問題意識の下にエビデンスに基づいた政策決定(Evidence Based Policy Making:EBPM)を行い、国民に対して説明責任を果たすこと」を重視する国になる必要がある。
本書はこの方向に向かう一歩として、社会保障の分野でエビデンスに基づいた現状の把握および政策提言を行った。
[本書の主なメッセージ]
・未来は変えられる。
・EBPMのプロセスを経れば、来るべき日本の超高齢社会も現在の想定とは違った展開をとりうる。
・われわれはどんな国を目ざしたいのか。
①60歳代を活用する国 ②新しい社会連帯をめざす国
③Ageing in place をかなえる国 ④子育て支援を強力に進める国
⑤弱者に手を差し伸べる国 ⑥所得格差の小さい国
⑦将来に対する投資を怠らない国
大多数の国民が支持する社会保障制度を構築するにあたり、国民の合意を得たい。
内容説明
エビデンスに基づいた政策決定(EBPM)で大多数の国民の支持を得れば、日本の高齢社会の「未来図」は変わる。われわれは日本をどんな国にしたいのか?弱者に手を差し伸べる国、将来に対する投資を怠らない国、新しい社会連帯をめざす国、子育て支援を強力に進める国、60歳代を活用する国、所得格差の小さい国…など。
目次
第1部 高齢者のいまを知る(長くなった寿命;子との同居は減少した;医療費の使われ方がますます重要に;低下してきた要介護率;日本のセーフティネットの強さは;社会保障と倫理)
第2部 高齢社会のゆくえ(2070年の高齢者像;平均寿命と自立寿命;高齢者医療費・介護費の動向;認知症高齢者数の推計)
第3部 “人生100年時代”への提言(人生100年時代の社会保障)
著者等紹介
府川哲夫[フカワテツオ]
1950年生まれ。1974年東京大学理系大学院修士課程修了、厚生省入省。1990年国立公衆衛生院に移籍。1996年国立社会保障・人口問題研究所部長。1998年保健学博士(東京大学)。2010年NPO法人福祉未来研究所共同代表。2013~2019年度武蔵野大学教授、2011~2020年度一橋大学大学院客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くらーく
kaz
-
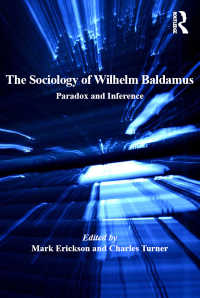
- 洋書電子書籍
- The Sociology of Wi…