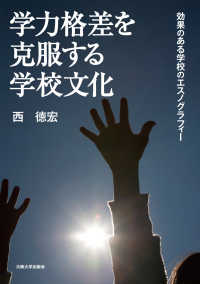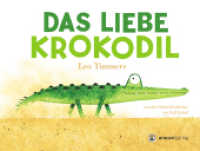出版社内容情報
防波堤・防潮堤は無駄なのか、価値があるのか?津波に対して粘り強いまちづくりとは?島国「日本」の津波防災のあり方を問う!
プロローグ
◆漆黒のハイウェイ/三月一一日午後二時四六分/横浜大学研究管理棟/被害状況入電/仙台入り
第一章 東日本大震災における巨大津波による被害実態
◆現地での最初の打ち合わせ/衝撃の光景/団体行動/女川/個人プレイ
●葉山教授の講義ノート(1)【東日本大震災における津波の高さ】
陸地に向かうにつれて高さが増す津波/津波のエネルギーの収斂/局所的にも違う津波の高さ/津波到達までの時間/コラム・津波の高さの定義/津波の高さと速度の簡便な計算方法
●堀場教授の講義ノート(1)【東日本大震災の地震の規模】
東日本大震災の地震の大きさとメカニズム/地殻変動と震度/津波発生のメカニズムと大きさ/地震と防護施設/コラム・マグニチュード/アスペリティモデルと地震の想定
第二章 防護施設の破壊
◆釜石湾口防波堤/理想と現実/防護施設と避難/田老
●葉山教授の講義ノート(2)【東日本大震災における被害の概要】
湾口防波堤の被害/海岸堤防の被害/建物の被害/漂流物と火災/コラム・津波の高さと構造物の破壊の関係/堤防の高さの決め方の難しさ
●葉山教授の講義ノート(3)【東日本大震災における人的被害】
東日本大震災における警報の実際/死亡者の年齢構成について/避難行動の開始について/死亡率/コラム・ハザードマップの役割/避難と警報慣れや防護施設に対する安心感
第三章 津波の威力
◆実験/防護施設の被災メカニズム/メディア対応/すべて流されたまち
●葉山教授の講義ノート(4)【津波の力】
津波と風波の違い/津波の力と勢い/津波のエネルギー/漂流物の力/コラム・水の力/津波による衝撃的な水の力
●葉山教授の講義ノート(5)【津波による構造物の破壊のメカニズム】
滑動と転倒現象/支持力破壊と洗掘/浮力と揚力/越流状況における安定性/コラム・どの程度の津波で人は流されるのか/構造物の安定性に関する簡便な計算
第四章 津波防護の考え方
◆三カ月後/津波専門委員会/防護施設の効果/二つの津波のレベル
●葉山教授の講義ノート(6)【津波に対する防護施設の低減効果】
釜石湾口防波堤の破壊状況と津波低減効果/湾口防波堤の締切効果/釜石湾口防波堤の津波低減効果のメカニズム/堤防の防護効果/コラム・津波と浴槽からあふれ出る水/津波に対する堤防の効果
●葉山教授の講義ノート(7)【津波に対する防護施設の役割】
防護施設による減災という考え方/防護施設の津波に対する粘り強い構造/防護施設による逃げ遅れと背後への影響/防護施設の特性/コラム・二つの津波レベル/堤防の高さと津波の発生頻度
第五章 防護施設のあり方
◆防護施設の役割/粘り強い堤防/津波シンポジウム/粘り強いまちづくり
●葉山教授の講義ノート(8)【津波からの早期復旧・復興】
津波被害を軽減する工夫/津波による産業の被災と復旧/業務継続計画の重要性/まち全体の復旧と復興/コラム・災害とは/高度化する社会と災害に対する脆弱性
●葉山教授の講義ノート(9)【避難と教育】
避難行動の開始における課題/避難経路と避難場所の課題/公助と自助・共助/防災教育と防災スペシャリスト/コラム・避難指示と避難勧告/避難と防災教育
第六章 巨大津波に対する備えとは
◆南海トラフ地震の想定/堤防が建設できないまち/避難訓練/防災と減災
●葉山教授の講義ノート(10)【観測と警報】
津波警報の歴史/東日本大震災における警報の課題/改善に向けて/予測精度の高度化に向けた観測網の整備/コラム・警報とオオカミ少年効果/避難に対する警報の活用
●堀場教授の講義ノート(2)【将来の巨大地震と津波】
南海トラフ地震の長期評価の検討方法/南海トラフにおける最大クラスの地震想定/日本海側の巨大地震と津波/地震と津波による複合災害への取り組み/コラム・日本と世界における巨大地震/今後の地震予知と津波予測の可能性
第七章 そして五〇年後
◆十数年後/二十数年後/そして五十数年後
●天川教授の講義ノート(1)【津波に対する最新の対策技術】
可動式の防波堤/可動式の陸域における堤防/漂流物対策/避難救命ボート/コラム・計算機を用いた浸水予測計算の取り組み/公助と減災
●天川教授の講義ノート(2)【沿岸減災設計演習】
防護施設の役割の整理/防護施設の高さと背後地の高さ/防護施設の決め方のパターン/合意形成の必要性/コラム・風化の問題と防護施設/防災・減災に対する〈まちづくり〉の役割
エピローグ
◆懐旧/釜石湾口防波堤
参考文献
あとがき
【著者紹介】
独立行政法人港湾空港技術研究所上席研究官
内容説明
防波堤・防潮堤は無駄なのか、価値があるのか?津波に対して粘り強いまちづくりとは?津波力に関する専門家が、調査や実験をもとに海に囲まれた日本の津波防災のあり方を問う!
目次
第1章 東日本大震災における巨大津波による被害実態(現地での最初の打ち合わせ;衝撃の光;団体行動 ほか)
第2章 防護施設の破壊(釜石湾口防波堤;理想と現実;防護施設と避難 ほか)第3章 津波の威力(実験;防護施設の被災メカニズム;メディア対応 ほか)
第4章 津波防護の考え方(三カ月後;津波専門委員会;防護施設の効果 ほか)
第5章 防護施設のあり方(防護施設の役割;粘り強い堤防;津波シンポジウム ほか)
第6章 巨大津波に対する備えとは(南海トラフ地震の想定;堤防が建設できないまち;避難訓練 ほか)
第7章 そして五〇年後(十数年後;二十数年後;そして五十数年後 ほか)
著者等紹介
有川太郎[アリカワタロウ]
独立行政法人港湾空港技術研究所上席研究官。東京大学工学部土木工学科1995年卒業。東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻博士課程2000年修了。博士(工学)。2000年に運輸省港湾技術研究所入省、その後、独立行政法人港湾空港技術研究所に組織名変更、2011年より現職。大規模な実験水槽を用いた津波実験や、京コンピュータなどを用いた数値シミュレーション手法の構築などが主な研究テーマである。2004年のスマトラ沖地震津波以後、津波の被災調査にも積極的に参加し、現場、実験、数値計算を組み合わせ、現象の解明に努める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。