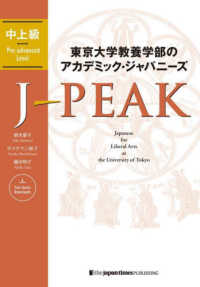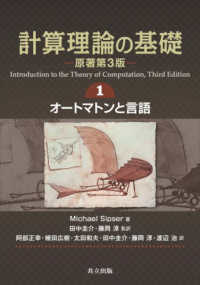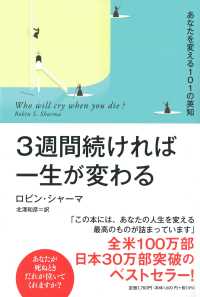出版社内容情報
診断は容易だが、治療がむずかしい摂食症。経験豊かな摂食症治療第一人者が書き下ろす、医師・心理士向けの実践的治療ガイド。
【目次】
第1章 準備編――診療を続けていくために
摂食症治療を好きになる
摂食症は病気(精神疾患)であることを理解する
性別
入院治療施設との連携
孤独にならない
第2章 診 断
診断基準
初回面接・初診時診察
検査(外来通院レベル)
臨床評価尺度
併存症の把握
診立てと、そのための情報収集
第3章 治療選択
はじめに:入院治療が必要かどうかの判断
身体的入院の絶対的適応および日常生活訓練
メンタル面の入院適応
第4章 外来治療
心理教育
食事日誌と体重測定
家族への説明
どのくらいの頻度で通院すべきか
身体的治療をどの程度すべきか
治療意欲を高める
認知行動療法の問題解決法を取り入れる
認知行動療法の認知構成法を取り入れる
対人関係療法を取り入れる:序論
対人関係療法を取り入れる:対人関係上の不和
対人関係療法を取り入れる:役割の移行
臨床心理士との協働
看護師、栄養士、PSWとの協働
第5章 診立てを活かす外来治療
はじめに:治療ガイドラインの限界と4つのプロトタイプ
高機能/完全主義プロトタイプ
抑制的/過剰コントロールプロトタイプ
感情統制障がい/コントロール不能プロトタイプ
神経発達性プロトタイプ
負けず嫌い、不食、そして哲学的不食
第6章 入院治療
摂食症専門病棟とは
低体重回復入院
教育入院
ガムテープブロック入院
第7章 リハビリテーション
集団療法からリハビリテーションへ
リハビリテーションの広がり
第8章 歴史
自らを飢餓に
産業革命、ブルジョア階級
第二次世界大戦,高等教育の一般化
第9章 回避・制限性食物摂取症
Great Ormond Street CriteriaからARFIDへ
ARFID有病率、併存症、予後、病因
ARFID1の臨床評価、治療
第10章 病因論――心理社会的病因論,生物学的病因論
病因論の変遷
ゲノム研究
セロトニン仮説-強迫性スペクトラム症仮説
その他の神経伝達物質の関与
脳のボリューム低下,認知機能
心理社会学的な側面と病像変化
併存症研究がもたらした種々のモデル
治療的観点から
第11章 疫学,予後
発病率、有病率
予後
中流階級の終焉と怒り
補遺
万引き--強烈な怒りをめぐって,精神科医がどう生き延びるか
内容説明
第一人者による実践の手引き。摂食症治療・教育にあたる医師、看護師、心理士、教師のためのコンパクトにして十分なガイド。
目次
第1章 準備編―診療を続けていくために
第2章 診断
第3章 治療選択
第4章 外来治療
第5章 診立てを活かす外来治療
第6章 入院治療
第7章 リハビリテーション
第8章 歴史
第9章 回避・制限性食物摂取症
第10章 病因論―心理社会的病因論、生物学的病因論
第11章 疫学、予後
補遺 万引き―強烈な怒りにあって、精神科医がどう生き延びるか
著者等紹介
永田利彦[ナガタトシヒコ]
壱燈会なんば・ながたメンタルクリニック院長。大阪市立大学(現・大阪公立大学)大学院医学研究科修了。医学博士。大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学准教授、ピッツバーグ大学メディカルセンターWPIC摂食障害専門病棟客員准教授等を経て2013年より現職。Academy for Eating Disorders、Eating Disorder Research Society、日本摂食障害学会(理事・前理事長)、日本不安症学会、日本うつ病学会、日本精神科診断学会(いずれも評議員)等に所属。摂食障害懇話会共同開催(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。