出版社内容情報
『「助けて」が言えない――SOSを出さない人に支援者は何ができるか』待望の続編
ヤングケアラー、貧困、虐待・ネグレクト、性暴力、いじめ、セクシュアルマイノリティ……現代の社会には、さまざまな逆境の中を生きている子どもたちが数多く存在しています。そうした子どもたちにとって、周囲に向かってみずからSOSを発し、助けを求めることは、とても難しいのが現実です。
それは、小さな「助けて」のサインを受け止めてもらえた、「助けて」と言ったら助けてもらえた経験を、子どもたちがもてていないからに他なりません。
大人にとって大切なのは、子どもたちが安心してSOSを出せるような環境を整え、不登校、自傷、オーバードーズ、ゲーム依存などの行為を「厄介な問題行動」と見なすのではなく、子どもなりのSOSのサインとして受け取ることです。
本書は全体を大きく二つのパートに分け、前半に、そうしたかかわりを目指す大人たちへのメッセージ、後半に、子どもたち自身へのメッセージを掲載しました。子どもにかかわるすべての人に、ぜひお読みいただきたい1冊です。
内容説明
かすかなSOSに耳を澄ませる。ヤングケアラー、虐待、性暴力、いじめ、不登校、自傷、オーバードーズ、ゲーム依存、セクシュアルマイノリティ―逆境を生きる子どもたち、そして周囲の支援者に伝えたいこと。
目次
1 「助けて」が言えない子どもたちにどうかかわるか―支援者へのメッセージ(大人は子どもの「助けて」を受け止められているか?―「SOSの出し方教育」の中で見えてきたこと;「助けて」の代わりに自分を傷つけてしまう心理―「自分でなんとかしなくては」から「言葉にならないままつながれる」への転換;「なんで私、こんな苦しいんやろう」と思ったけど―子どものかすかなSOSへのアンテナ;子どもたちは、なぜ教室で「助けて」と言えないのか;「助けて」と言えずに不登校を続ける子どもたち ほか)
2 「助けて」が言えないあなたへ―当事者へのメッセージ(誰も信用できないから「助けて」と言えない―孤立無援をどうサバイバルするか;自分を傷つけたい・消えたい・死にたいのに「助けて」と言えない;つらい記憶が頭から離れないのに「助けて」と言えない;「助けて」という気持ちをクスリと一緒に飲み込んでしまう;大人はわかってくれない―大好きなものを理解してもらえないあなたへ ほか)
座談会 子どもの自殺を防ぐために、私たちにできること(坪井節子×生越照幸×松本俊彦)
著者等紹介
松本俊彦[マツモトトシヒコ]
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。1993年佐賀医科大学卒業。横浜市立大学医学部附属病院にて臨床研修修了後、国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科を経て、2004年に国立精神・神経センター(現、国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所司法精神医学研究部専門医療・社会復帰研究室長に就任。以後、同研究所自殺予防総合対策センター自殺実態分析室長、同副センター長を歴任し、2015年より現職。2017年より国立精神・神経医療研究センター病院薬物依存症センターセンター長を併任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
ムーミン
マリリン
kanki
どりーむとら 本を読むことでよりよく生きたい
-
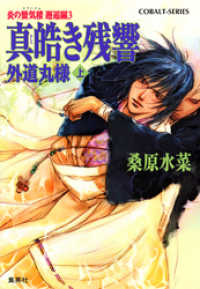
- 電子書籍
- 炎の蜃気楼 邂逅編3 真皓き残響 外道…
-
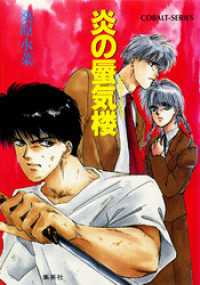
- 電子書籍
- 炎の蜃気楼 集英社コバルト文庫




