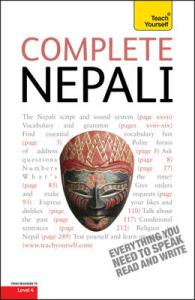出版社内容情報
傷つきを抱えながらも懸命に生きる児童養護施設の子どもたち。その心の機微や輝き、傍らで支える職員の思いを温かな筆致で描く。
内容説明
あたりまえの生活のなかで育まれる希望。家族と離れ、過酷な背景を抱えながらも力強く生きる児童養護施設の子どもたち。職員と共に笑ったり怒ったり泣いたりする日々を通じて成長や回復を遂げていく姿を、あたたかな筆致で描く。
目次
1 施設で暮らす子どもたち(初めての児童養護施設;物語の力 ほか)
2 傷つきと痛みに寄り添う(“あたりまえの生活”をめぐって;喪失の痛み ほか)
3 児童養護施設の現在と未来(遊ぶこと、楽しむこと;体験のアレンジャー(手配者)として ほか)
4 児童養護施設で働くこと(施設職員の専門性とは;記録を残す者と残される者 ほか)
著者等紹介
楢原真也[ナラハラシンヤ]
児童養護施設子供の家、統括職・治療指導担当職員。日本ソーシャルペダゴジー学会理事。大学院修了後、児童養護施設で児童指導員や心理職として勤務。子どもの虹情報研修センター主任を経て、2015年より現職。公認心理師、臨床心理士、人間学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
47
著者は、大学院で臨床心理学を学んだ後、児童指導員として、児童養護施設で現在も勤務を続けている。外部からはなかなか窺い知ることのできない施設の現状について、著者自身が子ども達と苦楽を共にし、彼らの成長を見届ける中で学んだ事を、様々なエピソードを交えて、率直な表現で語る。コラムとして、児童養護施設の概要、職員、子どもと家族、今後の施設のあり方などと共に、著者の児童養護施設政策への思いも語られる。日頃直接に目にすることは少ないけれども、日本の社会を根元で支える教育の一つの形として、多くのことを学ばせてもらった。2022/11/09
崩紫サロメ
29
著者は児童養護施設を運営する臨床心理士。もともとはエッセイとして連載されたものに児童養護施設の制度を解説したパートを加えたもの。やはり本文であるエッセイパートが面白い。多くの職員は施設にいる児童と同じ経験はしていない。そこで著者自身がどのようにその葛藤を乗り越えてきたか、というところで小説が多く登場する。司書課程か何かで小説とは「自分が体験していないことに想像力を巡らす」という意義があると学んだ。まさに、著者は日々そうして想像によって自分と児童をつなごうと苦戦する。読書の意味についても考えさせられた。2022/07/27
やん
5
図書館で見かけて。雑誌に連載されたエッセイに児童養護施設の制度等についての解説を加えたもの。著者は児童指導員や心理職として児童養護施設で働いてきた。施設で暮らす子どもたちに関するエピソードはメインではなく、この制度や中で働く職員の立場からの話が主だった。前にいた職場で、前職が児童養護施設の職員だった人がいた。詳しいことを聞く機会もなかったけど興味本位でいろいろ聞いてはいけないような気がした。そんな態度は良くないのかもしれない。日々の心温まるエピソードを共有する「にやりほっと」という取り組みが面白い。2024/05/21
たらこ
5
うまく言葉にならないが、気持ちに届く文章が多い本だった。現場は違えど、関わるこどもも多いので自分もこれからも頑張ろう。2022/06/07
オレンジstory
3
同じ施設職員という立場で、気持ちが重なる所と、自分がやっている日々の何気ないことの積み重ねに対して、励まされている感じがしました。自分自身も日々自己研鑽に努めたい。2023/09/19