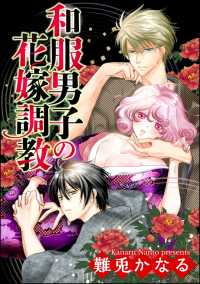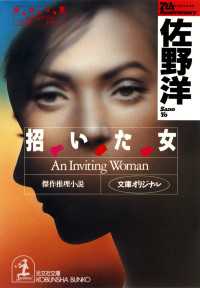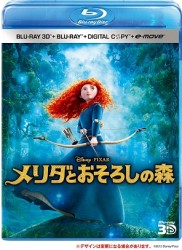内容説明
聞こえない人たちだけでなく、軽・中等度難聴や中途失聴者との心理臨床的かかわりを通して、コミュニケーションの本質を知る。
目次
第1章 福祉施設における聴覚障害者臨床―更生訓練のなかでの心理的支援
第2章 医療の現場から―チーム・アプローチの視点
第3章 集団精神療法の視点から
第4章 聴覚障害児のコミュニケーションと心理的援助―聾学校でのカウンセリングの取り組み
第5章 アイデンティティ形成と「ことば」
第6章 きこえない子どもたちと家族
第7章 軽・中等度難聴者の心理
第8章 中途失聴者の心理
第9章 心理面接における手話通訳
第10章 アセスメントについて
第11章 障害特性および実態把握のための試み
著者等紹介
村瀬嘉代子[ムラセカヨコ]
大正大学人間学部教授
河崎佳子[カワサキヨシコ]
京都女子大学現代社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
12
三回目の再読。この本はタイトルにあるとおり心理臨床学から見た聴覚障害者の心理状況を探ったもの。そのため難しい。日本のろう学校教育で手話が排除されていたことは良くなかったのではないか。耳は聞こえなくても手話を使う事で精神的にも良い影響をもたらすことが理解できた。2024/05/19
Francis
9
再読。これは専門書であり、臨床心理士などの専門家向けの書物ではあるので難しいのだけれども、難聴者が聴こえないというコミュニケーション障害を持つゆえに精神・心理面でも発達の遅れなどの障害をもたらしてしまうこと、そして著者をはじめとして専門家が聴覚障害者の心理面の歪みを治そうとする真摯な取り組みはよく理解できた。聴覚障害者への社会の理解はまだまだ遠いと感じることが多いので、この本に示された知見が少しでも社会に定着するよう切に願う。2018/09/24
Francis
4
ろう者・重度・中程度・軽度難聴者がコミュニケーション不全のために、どの様な心理状況にあるかをケースごとに考察している。2016/08/14
aki
0
1巻に続いて、参考になる2008/07/02