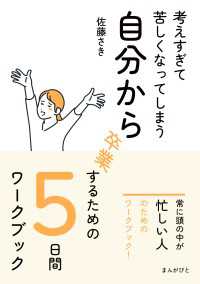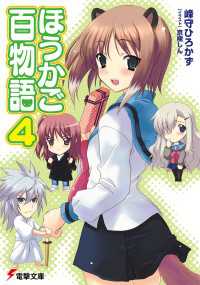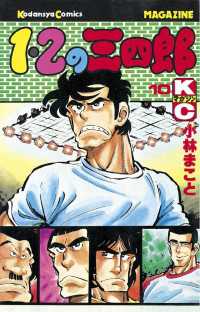内容説明
グローバルなテロリズムや貧困、紛争の脅威に立ち向かうのに、二つの異なるアプローチが存在する。一つが「パックス・アメリカーナ」だ。これは、必要ならば武力行使を辞さないアメリカ主導の安全保障、および開発のための国際秩序を意味する。もう一つのアプローチは、ヨーロッパやその他の世界で一般的な「グローバル・ガバナンス」である。これは、民主的な話し合いと責務の共有でグローバルな脅威に対応する国家・市民・ビジネスの三者の責任を具体的に示す規則や制度の総体を指す。本書では、後者のアプローチを支持する人たちに道筋を示し、多くの議論や証拠を提示して前者のアプローチの信憑性に疑問を投げかける。
目次
第1部 過去を振り返って(国際協力の責務;国際協力の歴史―一九四五年から今日まで;経済成長と政治体制;開発プロジェクト再考:大きいことはいいことなのか;人道支援の現状 ほか)
第2部 未来を考える(新しい対外援助のありかた;血の通った資本主義;グローバル・ガバナンスの未来;変革に向けた支持基盤の構築:チャリティの盛衰;組織の改革と自己変革 ほか)
著者等紹介
エドワーズ,マイケル[エドワーズ,マイケル][Edwards,Michael]
現在、マイケル・エドワーズ氏は、ニューヨークにある大手民間財団のひとつであるフォード財団でガバナンス・市民社会ユニット局長を務めている。現職に至る前は、英国オックスファム(南部アフリカの地域ディレクター)や英国セーブ・ザ・チルドレン(調査、評価、アドボカシーのディレクター)など、国際開発人道NGOでシニア・マネージャーとして15年に及ぶ活動を行い、その後、ワシントンにある世界銀行の市民社会ユニットのシニア・アドバイザーを務めた。エドワーズ氏の多数の著書は、NGO、市民社会、国際協力のあり方について示唆を与えている。オックスフォード大学を2科目最優等生として卒業し、ロンドン大学で、コロンビアにおける低所得者向け住居の市場の研究で博士号を受けている
杉原ひろみ[スギハラヒロミ]
1967年生まれ。日本アジア投資(株)を経て、1997年より2000年まで在ジンバブエ日本国大使館専門調査員として開発NGO向け資金協力等を担当。2001年から2002年まで米国開発NGO連合体「インターアクション」インターン。現在、ウェブサイト「地球に乾杯!NGO」を主宰。2005年より名古屋大学大学院国際開発研究科博士課程在籍。専門は開発NGOと政府の関係。1992年東京外国語大学朝鮮語学科卒業、1996年ロンドン大学大学院(SOAS)開発学修士
畑島宏之[ハタシマヒロユキ]
1964年生まれ。(財)国際開発高等教育機構、アフリカ開発銀行(於コートジボアール)などを経て、2001年国際金融公社(世界銀行グループ)入社。現在、独立評価グループ勤務。途上国での民間企業や民間プロジェクトがもたらす開発効果の事後評価を担当。1992年サセックス大学大学院(IDS)開発学修士。1999年ロンドン大学大学院金融経済学修士。専門は開発政策、開発金融、民間投資、金融リスク管理
鈴木恵子[スズキケイコ]
1973年生まれ。英国Overseas Development Institute(ODI)、UNESCO(東ティモール)を経て、2004年6月よりプログラムコーディネーターとしてJICA東京勤務。2000年英国ハル大学大学院開発地域研究修士。専門分野:開発社会学、地域開発(東南アジア)、援助アプローチ、人的資源開発
粒良麻知子[ツブラマチコ]
1979年生まれ。アムネスティ・インターナショナルのワシントンDC事務所、トランスペアレンシー・インターナショナル・ジンバブエ、在米日本国大使館経済協力班でのインターン等を経て、2004年から国連開発計画(UNDP)資金・戦略的パートナーシップ局にて、日本政府のUNDPへの拠出や基金の管理・調整業務を担当。2005年より在タンザニア日本国大使館専門調査員。2001年慶應義塾大学法学部政治学士、2003年ジョージ・ワシントン大学大学院国際開発学修士。専門はアフリカ政治、特に市民団体による政策提言活動と民主主義の定着の関連性について研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。