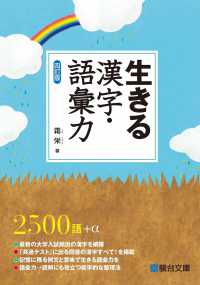出版社内容情報
自分の学問を平和のために役立てたいと研究生活を送ってきた著者が、国連憲章と日本国憲法に具現している不戦の理念を熱く説く。
第1部 概観
第1章 武力行使禁止原則の歴史的展開
――戦争の「正当原因」をめぐって
はじめに
1 伝統的国際法における戦争の地位
2 国際連盟規約における戦争の制限
3 不戦条約と侵略戦争の禁止
4 国際連合憲章における武力行使の違法化
5 現代的「正戦論」の帰結
第2章 武力行使禁止原則の現段階
――ICJの判断を手がかりに
はじめに
1 国連憲章における武力行使禁止原則の確立
2 武力行使禁止原則のコロラリー
3 自衛権
4 集団的自衛権
5 強制措置
6 むすび
第2部 個別国家による武力行使
第3章 個別的・集団的自衛権の行使
――対アフガニスタン武力行使の事例
1 問題提起
2 国際テロリズムは「戦争」か?
3 自衛を根拠とする武力行使
4 自衛以外の違法性阻却事由
5 一方的武力行使は世界秩序の将来に何をもたらすか
:結びに代えて
第4章 人道的干渉から「保護する責任」へ
――NATOによる対旧ユーゴと対リビア攻撃の事例
はじめに
1 予備的考察
2 伝統的国際法における人道的干渉
3 国連憲章体制と人道的干渉
4 慣習法としての人道的干渉
5 国家責任法における人道的干渉
6 立法論としての人道的干渉
7 国連における「保護する責任」論の展開:議論から「実施」へ?
8 むすびに代えて
第3部 安保理事会が「許可」した武力行使
第5章 湾岸戦争(1990?1991年)
はじめに
1 前史:イラン・イラク戦争に対する安保理事会の対応
2 イラクによるクウェート侵攻と安保理事会の初期の対応
3 「必要なすべての手段」の許可
4 安保理事会による第7章の権限の委任
5 決議687(1991)における対イラク要求
第6章 対イラク攻撃(2003年)
1 武力行使の正当化事由
2 イラクによる大量破壊兵器廃棄義務の履行状況
3 決議1441(2002)とその履行確保
4 自衛その他の正当化事由
5 開戦への道
6 武力攻撃とイラクの占領管理
7 イラク戦争の検証
第7章 人道的援助と平和維持活動による人道的活動
はじめに
1 「人道的援助の権利」の主張
2 安保理事会による人道的理由による武力行使の許可
3 強制措置の権限を与えられた平和維持活動による人道的活動
4 その後の動向
第4部 武力行使禁止原則の実効性をどのように回復するか
第8章 国連の課題と私たちの課題
はじめに
1 武力の限界と紛争原因への対処の必要性
2 安保理事会の活動の民主化のために
3 私たちにとっての課題
松井芳郎[マツイ ヨシロウ]
著・文・その他
目次
第1部 概観(武力行使禁止原則の歴史的展開―戦争の「正当原因」をめぐって;武力行使禁止原則の現段階―ICJの判断を手がかりに)
第2部 個別国家による武力行使(個別的・集団的自衛権の行使―対アフガニスタン武力行使の事例;人道的干渉から「保護する責任」へ―NATOによる対旧ユーゴと対リビア攻撃の事例)
第3部 安保理事会が「許可」した武力行使(湾岸戦争(1990~1991年)
対イラク攻撃(2003年)
人道的援助と平和維持活動による人道的活動)
第4部 武力行使禁止原則の実効性をどのように回復するか(国連の課題と私たちの課題)
著者等紹介
松井芳郎[マツイヨシロウ]
名古屋大学名誉教授。1941年京都府生まれ。1963年京都大学法学部卒業。1967年京都大学大学院法学研究科博士課程退学、名古屋大学法学部助手。1968年名古屋大学法学部助教授。1976年名古屋大学法学部教授。2004年立命館大学大学院法務研究科教授。2011年立命館大学定年退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。