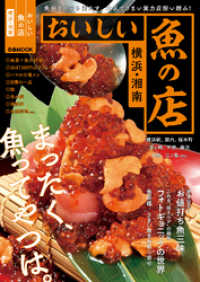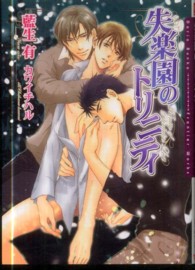内容説明
なぜ、ぶつかるのか。なぜ、わかり合えないのか。「民族の血統とその起源」で知る人類史のダイナミズム。
目次
第1部 アジア、中東(人種と民族のマトリックス;日本、台湾、チベットなど;中国、朝鮮など;東南アジア;中東。コーカサス;インド、アフガニスタン、中央アジアなど)
第2部 ヨーロッパ(白人はどこからやって来たのか;イタリア、フランス、スペインなど;ドイツ、イギリスなど;北欧、ベネルクス三国、スイス;ロシア、バルカン半島;東欧、バルト三国)
第3部 アメリカ、オセアニア、アフリカ(人類共通の祖先は黒人だったというのは本当か;北アメリカ、オセアニア;中南アメリカ;アフリカ)
著者等紹介
宇山卓栄[ウヤマタクエイ]
1975年、大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。代々木ゼミナール世界史科講師を務めたのち、著作家に。テレビ、ラジオ、雑誌、ネットなど各メディアで、時事問題を歴史の視点でわかりやすく解説(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
34
「血統とその起源」から人類史を読み解く、中南米やアフリカ諸国など欧米に支配された民族の視点から見た歴史も踏まえ、最新の遺伝子学の成果も押さえて多元的に解説する世界史。日本人を始めとする世界の各民族がどのような遺伝子構造から変遷を辿ったのか。それは侵略ややむを得ない事情による移動、文化の破壊や変容、迫害、強制、民族の混血や消滅の歴史でもあって、700p以上のボリュームでしたがどうしてそのようなことが起きたのか、各国史の中では見落とされがちな部分のアプローチもわりと多くて、とても興味深く読むことができました。2023/03/04
洋書好きな読書モンガー
20
図書館本。民族という言葉はracismにつながると嫌われているけれど、世界の歴史を知るには避けて通れない要素。言語と遺伝子解明によりどういう風に人々が移動などして来たのかを説明。文字が無い民族や読み書きが出来る人が1%に満たなかった長い中世とか文字で歴史を知るには限界があるが「言語」と遺伝子で色々わかって来た。2023年の本。日本語は世界的には珍しい文法を持つ言語で韓国語やフィンランド語など似ている言語は少数派だ。分厚い本なので歴史好きとしては手元に持ちたいと思った。2025/12/13
田中峰和
5
世界中ほとんどの地域で先住民と征服者が混血して現代の住人になっていることがよくわかる。インドヨーロッパ語族が世界に進出していくのは常識でも、本書で説明されるY染色体ハプログループによる分類は新たな学びがあった。中南米を征服したスペイン人は原住民を何十人も妾にして混血を増やした。メキシコ人の外見が白人と原住民に別れるが、コロンビアなど白人の外見が多いのは征服過程の違いであることも分かった。ベルベル人とアラブ系の混血が多い北アフリカ。征服は外見の違いだけでなく、イスラム対キリスト教の対立にまで影響する。2024/01/21
乱読家 護る会支持!
4
民族から見た世界史の本です。めちゃめちゃいい本ですが、700ページを超す太い本なので、乱読には向いていません(涙)。 民族の辞書的に家に置いておいたら、世界で紛争が起きた時に理解が早いと思います。 僕はさっそく購入することにしました。 強くオススメします! 2024/04/15
polythenepam_m
3
8 日本から遠くアフリカまで、全世界の民族の変遷を網羅したまさに民族全史。民族の成り立ち=国家の成り立ちで、古来からの民族の移動や侵略、民族同士の混血が積み重なって今の国家国境が形作られているんだなととても勉強になる。そして数々の紛争の原因とか国名の由来もなるほどなとこれまた勉強になる。 分厚いけど読む価値アリの一冊だった。2024/06/22