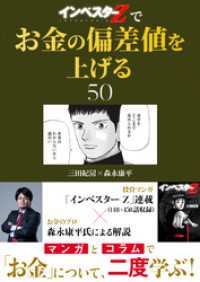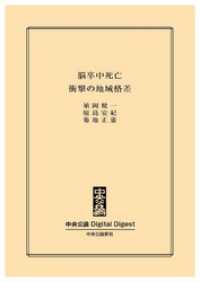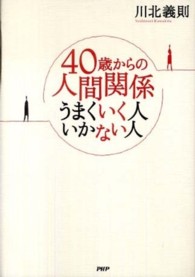出版社内容情報
「金融」の入門書は多くのビジネスマンに必要なものですが、意外なことに、初心者に向けて必要な項目をコンパクトに、わかりやすく解説。入門から応用の入り口までを網羅できる定番書。
内容説明
関連するテーマのすべてを図解入りで解説!基本から応用までやさしくわかる入門書の決定版!
目次
序章 金融は普通の人にも身近な存在
1章 企業活動と金融は深く関係している
2章 その名のとおり「金融機関」は金融の中心
3章 金融+市場=「金融市場」のしくみ
4章 投資家は金融にどう関わっているの?
5章 金融と経済の関係はどうなっているの?
6章 金融は政策や規制でどうコントロールされているのか
7章 金融+テクノロジー=「金融技術」は日進月歩
8章 金融がうまくいかないと大変なことになる!
著者等紹介
田渕直也[タブチナオヤ]
1963年生まれ。85年一橋大学経済学部卒業後、日本長期信用銀行に入行。デリバティブのディーリング、ポートフォリオマネジメント等に従事。その後、海外証券子会社であるLTCB International Ltdを経て、金融市場営業部および金融開発部次長。銀行本体のデリバティブ・ポートフォリオの管理責任者を務める。2000年にUFJパートナーズ投信(現・三菱UFJ投信)に移籍。現在はミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
77
金融論とはいうものの金融理論の教科書ではありません。世に言われる金融状況やその用語などをうまくかみ砕いて説明してくれています。ただやはり章によって読む順序を少し変えた方がいいのかもしれません。必ず図などが出ているので最近の若い人にはいいのかもしれません。必要最低限な経済用語の理解は必要です。2018/05/02
アルカリオン
13
p122 短期的には、為替相場には金利の影響が大きく、物価変動の影響は強くはあらわれません。ところが、長期的にみるとこの関係は逆転し、為替レートの変動はおおむね物価変動率に応じて動いているように見えるのです。デフレが長く続いた日本の円がずっと円高傾向にあったことはこの購買力平価の考え方によって説明することが可能です▼p145 金利の上昇によって、景気が過度に落ち込んでしまうことを「オーバーキル」といいます▼よく目にするのは半ばネットスラングとしての用法だが、ちゃんとした(?)使い方もあったのか。2025/01/27
ネクロス
6
身近で分かりやすい印象だが、業界用語の数に圧倒された。今まであまり金融を知ってこなかった身としては、覚える量が多い。なお、入門編だけあって、この本の知識のみで応用をするのは難しい。目的があっての調査の場合、単語を調査するミニ辞書的な使い方もいいと思う。2015/08/24
Zing
5
金融の入門書。専門用語の意味と、金融商品の概要が勉強できる本。最後の2章に「バブルは常にあって、いつ弾けるか分からん!」という内容が延々と書いてあって、好景気の今読むとリスクを念頭に置けるので良かった。慣れなさすぎて理解するのに時間がかかったが、金融の世界の共通言語を学ぶのに良い本だと思う。2016/12/30
mintia
4
図解や説明が分かりやすく、勉強になった。デリバティブについては難しく、もっと勉強する必要性を感じた。2020/09/15