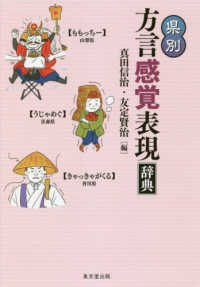内容説明
セルフ・マネジメント、マーケティング、イノベーション、会計、組織、IT、コミュニケーション…。自分がかかわる人の強みと創造性を引き出す本当のマネジメントによって、経営学を使いこなすことができる。ドラッカーが創設したマネジメントスクールで今でも受け継がれている「マネジメント」
目次
1 「セルフ・マネジメント」から始まる
2 マネージャーは何をめざすのか
3 マーケティングの本質―顧客創造的な会社とは
4 イノベーションという最強の戦略
5 会計とマネジメントの「つながり」
6 成果をあげる組織とチーム
7 情報技術とコミュニケーションについて本当に大事なこと
著者等紹介
藤田勝利[フジタカツトシ]
1996年上智大学経済学部卒業。住友商事株式会社、アクセンチュア社勤務後、2004年に米Claremont Graduate University P.F.Drucker Graduate School of Managementにて経営学修士号取得(成績優秀者表彰)。2005年よIT系ベンチャー企業にてマーケティング責任者、事業開発担当執行役員等を歴任。2010年経営コンサルタントとして独立し、Manage For Goodを創業。2013年PROJECT INTIATIVE株式会社設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
デビっちん
15
本書は、ドラッカーの学校で学んだ著者が実務を経て、これがマネジメントにはやっぱり大切だよね、という内容をまとめたモノです。マネジメントは、管理、統制よりも人間と創造に関わるモノです。マネジメントを創造ととらえると、メンバーの強みを発揮させ、弱みを無効化し、組織として成果に結びつける大切さに気づかされました。創造するには組み合わせるだけでなく、不要なモノを削ることも大切です。To stopリストの考えには、なんで今まで気づかなかったのかと少々凹みました。管理ではなく、創造するために必要な視点は?2016/07/01
kitten
9
図書館本。久しぶりのドラッカーの経営理論のお話。時代がこれだけ変わっても、ほとんどの話が通用するのが凄い。結局のところ、「人間」の話だから、なのかな。技術がどれほど進んでも、人間の感情はかわらないものだから。2025/05/10
りさ
3
マネジメントとは管理ではなく創造である。サービス業は人件費のコストが大きな割合を占める。知的労働者の活かし方の原則は、強みを活かすことだという。問題点、課題に目が向かいがちだが、自分の強みを組織に活かす術を探ることが自分のやりがいにとっても、組織の益にもつながる。2019/12/08
mmiyoshi
3
ドラッカーの導入として良書であると考える。 各章で具体的な事例を挙げ、その点について読者に考えさせる。 また「マネジメント」「イノベーション」という言葉について考えさせる一冊。2014/07/30
Akitoshi Maekawa
3
マネジメントとは「管理」ではなく、「貢献する責任」とするドラッカーの教えを経営のケースを交えながら説明していく一冊。非常におすすめ。戦略思考とイノベーション思考の混ざる点や、システム開発とマネジメントの関係をひも解いているあたりが興味深く、また周囲の課題感と相まって興味深かった。「マネジメントが目指すものは、つまるところ、自由でいきいきと躍動する人と組織を創り、正課につなげること」。肝に銘じよう。2014/02/21