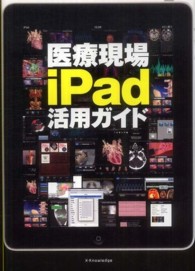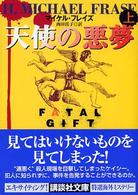目次
第一期線(九条新道(花園橋)
境川町 ほか)
第二期線(大阪駅前(梅田停車場)
桜橋 ほか)
第三期線(本田町一丁目;川口町 ほか)
第四期線(動物園前(天王寺公園南口)
阿倍野橋 ほか)
期外線(野田阪神電車前;鶴町二丁目 ほか)
著者等紹介
辰巳博[タツミヒロシ]
昭和2年、大阪市阿倍野区生まれ。兵庫県西宮市在住。昭和25年大阪大学工学部電気工学科を卒業して大阪市交通局に就職し、大阪市電および地下鉄の車両技術を担当。特に昭和44年の大阪市電全面廃止時には、幹部職員としてその幕引きに奮闘。昭和47年に同局森之宮車両工場長から大阪市立電気科学館長に転任し、昭和57年に定年退職。現在、伊丹市立こども文化科学館顧問
福田静二[フクダセイジ]
昭和24年、京都市上京区生まれ。現、京都府長岡京市在住。市電交差点のすぐ近くに生まれ、市電のクロッシング音を耳に育つ。学生時代は蒸気機関車を中心に、各地の鉄道の撮影に熱中する。現在もその余韻を楽しみつつ鉄道写真の撮影を続ける。勤務先の印刷会社では、編集制作の仕事を行う。本書では、編集と現状の撮影を担当。同志社大学鉄道同好会OB会所属
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 【無料試し読み】ムクカノ:無垢で無口な…
-
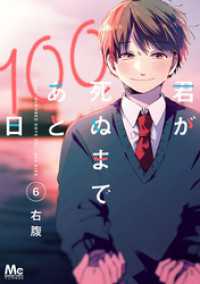
- 電子書籍
- 君が死ぬまであと100日 単行本版 6…